地域包括支援センターで働く保健師の仕事は、とてもやりがいがある反面、大きな負担を感じることも多いですよね。
業務量の多さや人間関係のストレス、専門職としての役割とのギャップに悩み、「もう辞めたい…」と感じる人も少なくありません。
今回は、地域包括支援センターの保健師が辞めたいと感じる理由と、その対策について詳しく解説します。
この記事を読めば、仕事の負担を減らす方法や転職・異動の選択肢が分かり、自分に合った働き方を見つけるヒントになります。
今の環境を改善したい方や、新しいキャリアを考えている方は、ぜひ最後まで参考にしてください。
地域包括支援センターの保健師が辞めたいと感じる理由
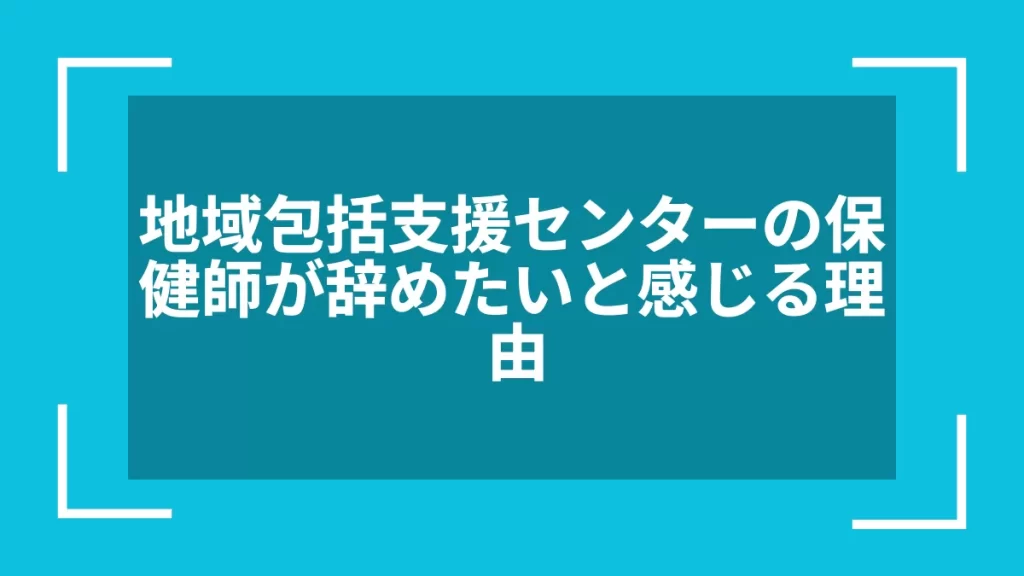
業務量の多さと負担の重さ
多くの地域包括支援センターで働く保健師が「業務量が多すぎる」と感じています。
特に、要支援者や高齢者との対応、ケアマネージャーや関係機関との連携、行政への報告業務など、多岐にわたる業務を限られた人員でこなさなければなりません。
その結果、心身ともに疲れ果ててしまう人も少なくありません。
- 相談対応が膨大…地域の高齢者や家族からの相談が絶えず、1日に何件も対応することが求められる
- 訪問業務の負担…自宅訪問や施設訪問が多く、移動時間も含めると1日のスケジュールが非常にタイト
- 事務作業が多い…記録や報告書の作成、会議の準備など、デスクワークに追われることが多い
- 関係機関との調整が難しい…ケアマネージャーや医療機関、行政と連携する機会が多く、調整に時間がかかる
- 突発的な対応が必要…緊急対応が求められるケースもあり、予定通りに業務が進まないことが多い
これらの要因が重なり、常に時間に追われる状況が続くことで、辞めたいと感じる保健師が多くなっています。
人間関係のストレス
地域包括支援センターでは、さまざまな職種の人と関わるため、人間関係のストレスを感じやすい環境です。
特に、多職種連携が重要な職場であるため、意見の食い違いや業務分担のバランスが問題になることもあります。
- 上司や同僚との関係…職場の雰囲気や人間関係が悪いと、業務がさらに苦しく感じられる
- ケアマネージャーとの意見の違い…支援方針の違いによって、意見がぶつかることがある
- 行政とのやりとりの難しさ…制度の変更や報告義務の多さで、行政との調整に苦労することがある
- 利用者や家族からのクレーム…期待に応えられない場合、厳しい意見を受けることもある
- 他職種との連携の難しさ…医師や看護師、介護職との連携がうまくいかないと、業務がスムーズに進まない
こうした人間関係のストレスが積み重なると、精神的に疲れてしまい、仕事を辞めたくなることにつながります。
専門職としての役割のギャップ
保健師は専門知識を持った職業ですが、地域包括支援センターでは「理想と現実のギャップ」に悩むことがあります。
公衆衛生の視点で住民の健康を支える仕事をしたいと考えていたのに、実際には介護保険制度の説明や事務作業が中心になることも多いのです。
- 保健師らしい業務が少ない…公衆衛生の視点で働きたいのに、福祉寄りの業務が多くなる
- 健康支援よりも事務作業が多い…制度説明や申請手続きなど、保健師本来の業務と異なる内容が多い
- 専門知識が活かしにくい…自分のスキルを活かせる場面が少なく、やりがいを感じにくい
- 求められる役割が広すぎる…地域の保健活動だけでなく、介護や福祉全般の知識が必要
- 成果が見えにくい…長期的な支援が必要なため、すぐに結果が出ず、達成感を得にくい
このような現状が、モチベーションの低下や仕事への不満につながり、辞めたいと感じる保健師が増えています。
給与や待遇への不満
保健師の仕事は責任が大きく、業務量も多いですが、それに見合った給与や待遇が得られていないと感じる人も多いです。
特に、公務員として働く場合は昇給のスピードが遅く、モチベーションを維持するのが難しいこともあります。
- 給与が低い…仕事内容に比べて収入が見合っていないと感じることがある
- 昇給が遅い…公務員としての給与体系では、昇給のペースが遅く感じる
- 残業代が支給されないこともある…みなし労働が多く、サービス残業が発生しやすい
- ボーナスや手当が少ない…他の職種と比べると、待遇面での差が気になる
- 労働時間に対する対価が低い…業務負担が大きいのに、報酬が見合わないと感じることがある
このような状況が続くと、より給与や待遇の良い職場を求めて転職を考える保健師が増えてしまいます。
精神的なプレッシャー
地域包括支援センターの保健師は、利用者の命や健康に関わる重要な仕事を担っています。
そのため、常に大きな責任を感じながら働くことになり、精神的なプレッシャーが強くなります。
- 命に関わる判断を求められる…対応の仕方によっては、利用者の健康状態が悪化することもある
- 家族からの期待が大きい…「何とかしてほしい」と強く求められることが多い
- 支援の成果が見えにくい…すぐに結果が出ないため、達成感を得にくい
- 精神的な負担が大きい…高齢者や要支援者の状況が改善しないと、自責の念を感じることがある
- ストレス発散の機会が少ない…忙しくて、気分転換する時間が取れない
精神的なプレッシャーが続くと、心身の健康に影響を与え、仕事を辞めたいと考える人が増えてしまいます。
辞めたいと感じたときに考えるべきポイント
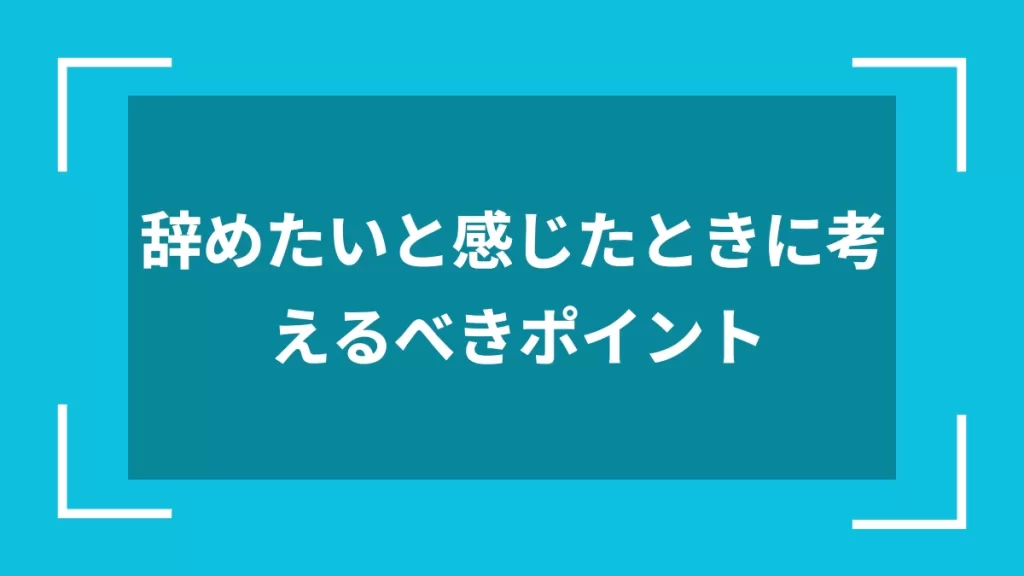
本当に辞めるべきかの判断基準
仕事を辞めたいと感じたとき、まずは冷静に「本当に辞めるべきなのか」を考えることが大切です。
感情的になってしまうと、後悔する選択をしてしまう可能性があります。
以下のポイントを確認しながら、自分にとって最適な選択をしましょう。
- 仕事のストレスが耐えられないほど大きいか…身体的・精神的な健康が著しく悪化しているかどうかを確認する
- 職場環境の改善が見込めるか…異動や業務改善の相談で状況が変わる可能性があるか考える
- 他にやりたい仕事があるか…次のキャリアプランを具体的に描けるかを確認する
- 経済的に辞めても問題ないか…貯蓄や生活費の見通しを立て、無理なく転職できるか考える
- 一時的な感情で決めていないか…短期間の不満や一時的なトラブルで判断していないかを振り返る
これらをしっかり考えた上で、今の職場で改善できることがあるなら試してみることも重要です。
仕事の負担を軽減する方法
辞める前に「仕事の負担を減らす方法」を試してみるのもひとつの手段です。
少しの工夫でストレスが軽減されることもあります。
- 業務の優先順位を明確にする…重要な業務から取り組み、無駄な作業を減らす
- 上司や同僚に相談する…負担が大きい業務について調整できるか話し合う
- タスク管理を工夫する…スケジュール管理を見直し、効率的に働けるようにする
- 仕事のやり方を改善する…効率的な方法を見つけて、業務時間を短縮する
- 適度に休憩を取る…集中力を維持し、無理のない働き方を心がける
このような工夫をすることで、少しでも負担を軽くし、働きやすい環境を作ることができます。
相談できる相手を見つける
仕事の悩みを抱え込むのはよくありません。
誰かに話すことで解決策が見つかることもあります。
信頼できる人に相談し、自分にとって最善の方法を探しましょう。
- 同僚や上司に相談する…職場の状況を知っている人に意見を聞くと、現実的なアドバイスがもらえる
- 家族や友人に話す…仕事とは関係のない立場の人の意見が、新しい視点を与えてくれる
- 専門家に相談する…キャリアカウンセラーやメンタルヘルスの専門家に相談すると、的確なアドバイスが得られる
- 転職エージェントに相談する…現状を踏まえた上で、適切な転職先を紹介してもらえる
- 公的な相談機関を利用する…自治体の労働相談窓口などを活用し、客観的な意見を聞く
誰かに相談することで、新しい解決策が見つかるかもしれません。
一人で悩まず、周囲の人の意見を取り入れてみましょう。
キャリアの選択肢を整理する
仕事を辞めるかどうかを決める前に、自分のキャリアについて整理しておくことが大切です。
現在の仕事を続けるべきか、転職すべきか、どのような道があるのかを明確にしましょう。
- 今の仕事を続けるメリットとデメリットを整理する…辞めることのリスクや、今の職場に留まるメリットを考える
- 自分の強みやスキルを見直す…転職を考える際に、自分の市場価値を知る
- 他の職種や職場の情報を調べる…保健師としてのスキルを活かせる職場を探してみる
- 転職する場合の準備を始める…履歴書や職務経歴書の準備、求人情報のチェックを始める
- 新しいスキルを学ぶ…今後のキャリアの幅を広げるために、資格取得や勉強を検討する
将来のキャリアを明確にすることで、自分にとってベストな選択ができるようになります。
転職と公務員としての将来性
地域包括支援センターの保健師は、公務員や行政職に近い立場にあることが多いです。
そのため、辞めることで将来的な安定を失うのではないかと不安になる人もいるでしょう。
転職する場合、公務員のキャリアをどう活かすかを考えることが重要です。
- 公務員としての経験が評価される職種を探す…行政関係や公的機関での仕事を視野に入れる
- 民間企業でのキャリアも考える…企業の産業保健師など、公務員以外でも活かせる仕事を探す
- 公務員試験を受け直す…他の自治体や職種で公務員として働く選択肢を考える
- 医療や福祉分野の転職先を調べる…病院やクリニック、介護施設なども選択肢に入れる
- フリーランスや独立の道を模索する…独立して健康指導やセミナー講師をする道もある
公務員としての経験を活かしながら、安定したキャリアを築く方法を考えることが大切です。
メンタルヘルスの維持方法
仕事を続けるにしても辞めるにしても、心の健康を守ることは非常に重要です。
ストレスを溜め込みすぎないように、日常生活の中でできる対策を実践しましょう。
- 適度に休息を取る…疲れを感じたら、しっかりと休むことが大切
- 趣味やリラックスできる時間を作る…仕事以外に楽しめることを見つける
- 運動を取り入れる…軽い運動をすることで、ストレスを発散できる
- 人と話す機会を増やす…一人で抱え込まず、誰かに相談する
- 必要なら専門家の助けを求める…カウンセリングなどを活用して、心のケアをする
メンタルヘルスを大切にすることで、より良い働き方や生き方が見つかるはずです。
地域包括支援センターの保健師が取れる解決策
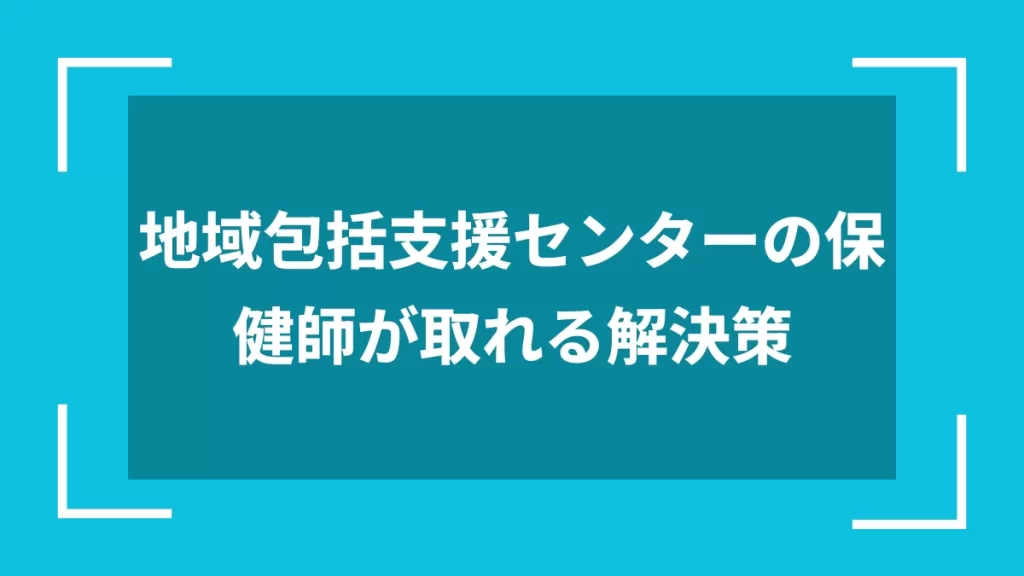
業務改善を上司や同僚と話し合う
業務の負担が大きいと感じたときは、まず上司や同僚と話し合い、業務改善の方法を模索することが大切です。
職場の環境を変えることで、負担を減らすことができるかもしれません。
- 業務の優先順位を見直す…重要な仕事に集中し、負担を減らす方法を話し合う
- タスクの分担を明確にする…一人で抱え込まず、チームで協力できる体制を作る
- 無駄な業務を削減する…効率化できる業務がないかを確認し、不要な作業を減らす
- 会議や報告の時間を短縮する…必要な情報だけを共有し、業務時間を有効に使う
- 業務改善の提案をする…新しいシステムの導入や手続きの簡略化などを提案する
小さな改善でも積み重ねることで、働きやすい環境を作ることができます。
ストレスを軽減する工夫
ストレスが溜まると仕事へのモチベーションが低下し、辞めたくなる原因になります。
自分でできるストレス軽減の工夫を取り入れてみましょう。
- こまめに休憩を取る…短い時間でもリラックスできる時間を確保する
- 仕事とプライベートの切り替えを意識する…オンオフをはっきりさせ、家では仕事のことを考えない
- 趣味やリフレッシュの時間を作る…楽しいことをする時間を意識的に増やす
- 適度な運動を取り入れる…体を動かすことでストレス発散につながる
- 職場の人間関係を良くする…良好な関係を築くことで、働きやすさが向上する
ストレスをうまくコントロールすることで、気持ちが軽くなり、仕事に前向きに取り組めるようになります。
スキルアップや資格取得の活用
今の仕事に対するモチベーションを高めるために、スキルアップや資格取得を目指すのも一つの方法です。
将来のキャリアの幅を広げるためにも、積極的に学ぶ姿勢が大切です。
- 新しい資格の取得を目指す…ケアマネージャーや福祉関連の資格を取ることで、キャリアアップにつながる
- 研修やセミナーに参加する…最新の知識やスキルを学ぶことで、仕事に役立てる
- 専門分野を深める…保健指導や高齢者支援の知識を強化し、より専門的な業務に取り組む
- 他職種との連携を学ぶ…多職種連携のスキルを磨くことで、業務がスムーズになる
- キャリアコンサルタントに相談する…今後のキャリアについて、専門家にアドバイスをもらう
スキルアップを目指すことで、新しい道が開け、今の仕事に対する不満を軽減できるかもしれません。
異動や配置転換を考える
今の職場環境がどうしても合わない場合は、異動や配置転換を考えるのも一つの選択肢です。
環境を変えることで、働きやすくなる可能性があります。
- 異動希望を上司に相談する…自分の希望を伝え、適切な部署への異動を検討する
- 別の自治体や機関で働くことを考える…同じ仕事でも、職場環境が変わるだけで大きな違いがある
- 他の職種に挑戦する…保健師としての経験を活かし、違う分野に進むのも一つの方法
- 短期間の休職を検討する…一度リフレッシュしてから、改めて今後の働き方を考える
- 配置転換の制度を調べる…行政機関や企業によっては、配置換えの希望を出せる制度がある
無理に我慢し続けるのではなく、自分に合った環境を見つけることが大切です。
転職を視野に入れた準備
どうしても仕事が合わないと感じたら、転職を視野に入れることも考えてみましょう。
焦らず計画的に準備を進めることが大切です。
- 自己分析を行う…自分の強みややりたいことを整理する
- 転職市場の情報を調べる…保健師の求人や他職種の仕事についてリサーチする
- 転職エージェントを活用する…プロのアドバイスを受けながら、自分に合った職場を探す
- 履歴書や職務経歴書を準備する…転職活動をスムーズに進めるために、書類の準備を始める
- 面接対策を行う…自分の経験やスキルをしっかりアピールできるようにする
しっかりと準備を進めれば、より良い職場で働くことができるようになります。
労働環境の改善を求める方法
職場の環境が厳しすぎる場合、改善を求めることも重要です。
労働環境が整えば、辞める必要がなくなるかもしれません。
- 労働基準法を確認する…自分の働き方が法律に違反していないかチェックする
- 労働組合に相談する…職場の改善を求めるために、組合のサポートを受ける
- 上司や管理職に意見を伝える…働きにくい点を具体的に伝え、改善を求める
- 行政の相談窓口を利用する…労働問題に関する相談ができる窓口を活用する
- 同僚と協力して改善を求める…一人で動くのが難しい場合は、同僚と協力する
労働環境を改善することで、無理なく働ける環境が整う可能性があります。
自己成長のためのマインドセット
辞めたい気持ちがあるときこそ、前向きな考え方を持つことが大切です。
仕事を通じて成長することで、新しい視点が生まれるかもしれません。
- 成長の機会と考える…厳しい状況も、自分を成長させるチャンスだと考える
- 小さな成功を積み重ねる…日々の達成感を大切にし、モチベーションを維持する
- 新しい目標を設定する…仕事の中でやりがいを見つける
- 周囲のサポートを受け入れる…一人で抱え込まず、助けを求める
- ポジティブな習慣を身につける…前向きな考え方を意識する
自分自身の成長を意識することで、今の仕事に対する見方が変わるかもしれません。
地域包括支援センター以外の保健師のキャリアパス
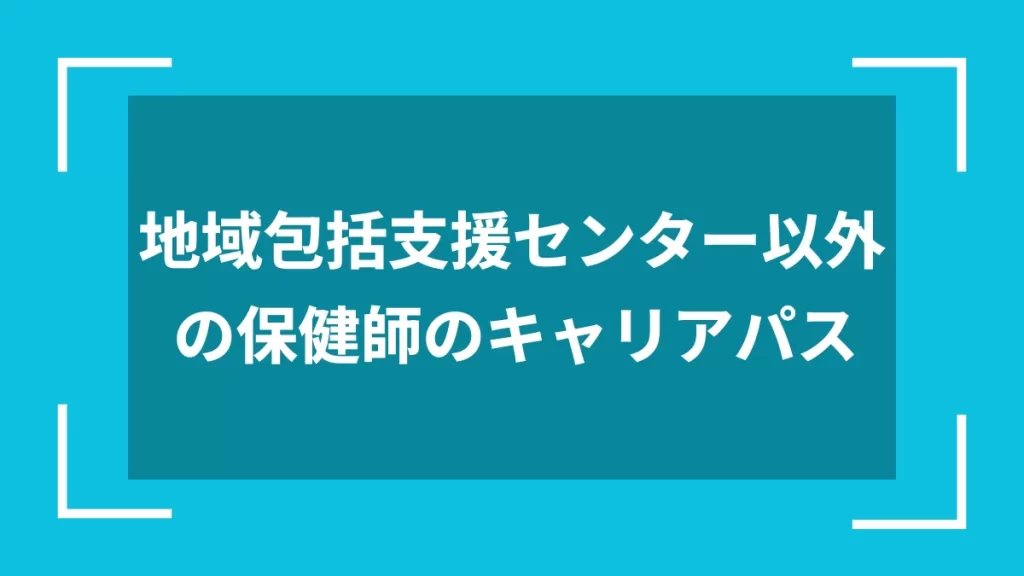
病院やクリニックの保健師
地域包括支援センターを離れた後の選択肢の一つとして、病院やクリニックで働くことが挙げられます。
医療機関での保健師の役割は、患者の健康管理や生活習慣の指導、院内の感染対策など多岐にわたります。
- 病院の保健指導…生活習慣病予防のための指導や患者への健康相談を行う
- 院内感染対策…病院内での感染予防策を管理し、医療スタッフに指導する
- 退院支援…患者が退院後も適切なケアを受けられるように支援する
- クリニックでの健康相談…地域の患者に向けた健康相談や予防医療を推進する
- 企業との連携…産業保健師のような役割を担い、従業員の健康管理をサポートする
病院やクリニックでの勤務は、医療の現場により近い環境で働きたい人に適しています。
企業の産業保健師
企業で働く「産業保健師」という選択肢もあります。
企業内で従業員の健康管理を担当し、職場環境の改善や健康診断の実施、メンタルヘルス対策を行う仕事です。
- 従業員の健康相談…体調管理や生活習慣の改善をサポートする
- 健康診断の実施・フォロー…企業の定期健康診断を管理し、結果の説明を行う
- 職場の安全衛生管理…労働環境の改善や安全対策を講じる
- メンタルヘルスケア…ストレスチェックの実施やメンタルヘルス相談を担当する
- 長時間労働の管理…過労による健康被害を防ぐための指導を行う
産業保健師は、夜勤がなく、安定した勤務時間で働けるため、ワークライフバランスを重視する人におすすめの職種です。
行政機関の別部署への転職
地域包括支援センターで培った経験を活かし、行政機関の別部署で働くことも可能です。
特に、保健所や市役所などでは、保健師の知識やスキルが求められています。
- 保健所での健康指導…地域住民への健康教育や感染症対策を行う
- 市役所の健康推進課…自治体が実施する健康増進プログラムの企画・運営を担当する
- 子ども・家庭支援センター…母子保健や児童福祉に関わる業務を行う
- 高齢者福祉の政策立案…地域の高齢者支援に関する制度設計に携わる
- 防災・危機管理部門…災害時の保健指導や医療支援を担当する
行政機関の別部署で働くことで、公衆衛生や福祉の分野で広く活躍することができます。
フリーランスや独立の道
保健師としてのスキルを活かし、フリーランスや独立するという選択肢もあります。
特に、健康指導やカウンセリング、オンライン講座の開設など、多様な働き方が可能です。
- オンライン健康指導…インターネットを活用して、全国の人に向けた健康アドバイスを提供する
- セミナー講師…企業や自治体向けに、健康管理やメンタルヘルスについての講義を行う
- 個人向け健康カウンセリング…ダイエットや生活習慣改善の個別指導を実施する
- 執筆活動…健康に関するコラムや書籍の執筆を行う
- YouTubeやSNSでの情報発信…健康に関する知識を発信し、フォロワーを増やす
フリーランスは自由度が高い反面、収入が安定しにくいデメリットもあります。
準備をしっかり行った上で挑戦すると良いでしょう。
保健師以外の医療・福祉職への転職
保健師の資格や経験を活かして、他の医療・福祉職に転職することも可能です。
例えば、看護師、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士などの職種が考えられます。
- 看護師への転職…看護師資格を取得し、病院やクリニックで働く
- ケアマネージャーへの転職…高齢者や障害者のケアプランを作成する仕事に就く
- 社会福祉士としてのキャリア…福祉施設や行政機関での相談支援業務を担当する
- 訪問看護師として働く…利用者の自宅に訪問し、医療ケアを提供する
- 健康運動指導士として活躍…運動療法を指導し、生活習慣病予防に貢献する
医療・福祉業界の知識を活かせるため、新しい分野にチャレンジしやすいのが特徴です。
資格を活かした新たな働き方
保健師の資格を活かしつつ、新しい働き方を模索するのも一つの選択肢です。
最近では、オンラインでの活動や副業としての仕事も増えています。
- オンラインカウンセラー…健康相談やメンタルヘルスケアをオンラインで提供する
- ライター・ブロガー…健康や医療に関する記事を執筆し、収入を得る
- 企業研修の講師…企業向けの健康管理やストレス対策の研修を担当する
- 健康食品やサプリメントの監修…企業の商品開発に関わる
- 地域コミュニティでの活動…健康イベントの企画や運営を行う
これまでの経験を活かしながら、新しい分野で活躍することも可能です。
保健師経験を活かせる民間企業
民間企業でも保健師のスキルを活かせる職場があります。
特に、製薬会社やヘルスケア関連の企業では、専門的な知識を求めています。
- 製薬会社のメディカルアドバイザー…医療従事者向けに製品の情報提供を行う
- 健康食品会社のアドバイザー…商品開発やマーケティングに関わる
- 保険会社の健康相談員…契約者向けに健康管理のアドバイスをする
- ウェルネス企業のコンサルタント…企業の健康経営をサポートする
- フィットネス業界での活動…健康指導やトレーニングプログラムを企画する
保健師の知識を活かしながら、幅広い分野で活躍できる可能性があります。
まとめ

地域包括支援センターの保健師が辞めたいと感じる理由と対策について解説しました。
改めて重要なポイントを整理します。
- 業務量が多く、負担が大きい…タスクの見直しや上司との相談が必要
- 人間関係のストレスがある…適度な距離を保ち、信頼できる人に相談する
- 専門職としての役割とのギャップ…スキルアップや異動の選択肢を考える
- 給与や待遇に不満がある…転職を視野に入れ、条件の良い職場を探す
- 精神的なプレッシャーが大きい…ストレス管理を意識し、心身の健康を優先する
- 転職や異動の選択肢がある…病院や企業、公的機関など、キャリアの可能性を広げる
- 働き方を見直すことが大切…辞める前に業務改善や負担軽減の方法を試す
今の職場で改善できることがないか考えつつ、新しいキャリアの可能性も視野に入れて行動しましょう。
自分にとってベストな働き方を見つけることが、心身の健康と充実した人生につながります。







