コロナ禍で保健師の仕事がとても大変になりましたよね。
感染者の対応やワクチン業務が増え、残業や休日出勤が当たり前になった人も多いのではないでしょうか。
そんな厳しい状況が続く中で、「もう続けられない」と退職を考える保健師も増えています。
今回は、コロナ禍での保健師の退職事情と、転職を成功させるためのポイントについて解説します。
なぜ退職を決意する人が増えているのか、どんな転職先があるのか、スムーズに転職するためには何をすべきかを詳しくお伝えします。
転職を考えているけれど不安がある人も、この記事を読めば自分に合った新しい働き方を見つけるヒントが得られるはずです。
退職を決断する前に、ぜひ最後まで参考にしてください。
コロナ禍における保健師の退職事情とは
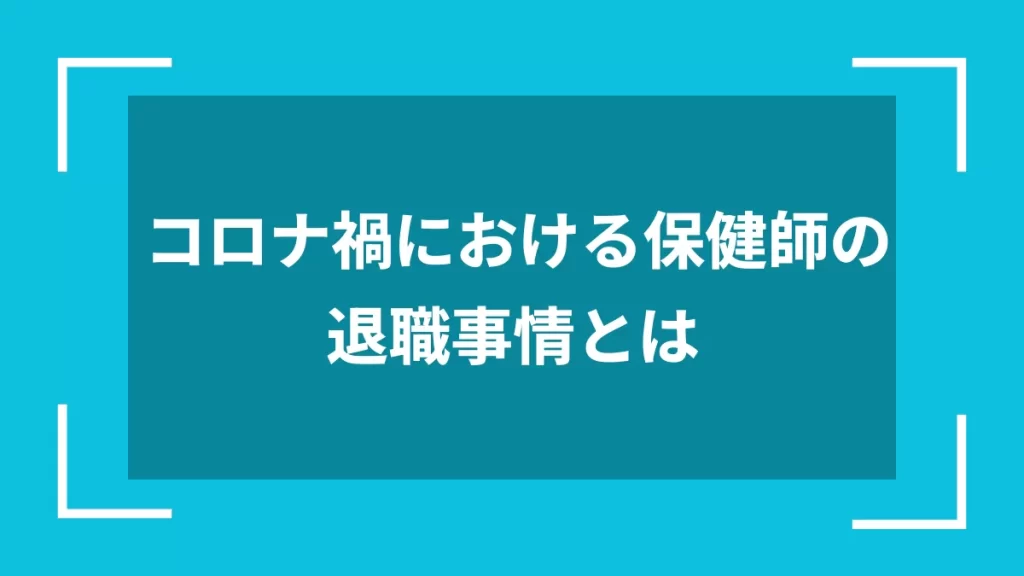
コロナ禍で保健師の業務負担が増加した背景
コロナ禍により、保健師の業務は急激に増加しました。
特に感染拡大のピーク時には、通常業務に加え、感染者の健康管理や疫学調査、ワクチン接種の調整など多くの新たな業務が発生しました。
その結果、多くの保健師が過労に苦しみ、退職を考える人が増えました。
具体的に、保健師の業務負担が増加した理由を以下に示します。
- 感染者の健康管理:毎日大量の感染者と接触し、健康状態を確認する必要があった
- 疫学調査の実施:感染経路を特定するために、膨大な聞き取り調査を行わなければならなかった
- ワクチン接種業務の負担:予約受付や副反応対応など、本来の業務以外の負担が増えた
- 市民からの問い合わせ対応:電話が鳴り止まず、一人ひとりに丁寧に対応する必要があった
- 長時間労働の常態化:休日出勤や夜間対応が増え、体力的・精神的に疲弊した
このような状況が続いた結果、退職を選択する保健師が増えたのです。
過労や精神的負担による退職者の増加
保健師の退職理由の中でも、大きな割合を占めるのが過労と精神的負担です。
コロナ禍では、対応が間に合わないほどの業務量に追われ、心身ともに疲れ切ってしまうケースが多く見られました。
特に、以下のような理由でメンタルが限界に達した人が増えました。
- 終わりの見えない業務:常に感染状況が変化し、対応し続ける必要があった
- 市民からのクレーム対応:感染対策に不満を持つ市民の怒りを受けることが多かった
- 家族や友人との時間が取れない:長時間勤務が続き、プライベートの時間が確保できなかった
- 医療現場との板挟み:病院側と行政の要望が異なり、調整に苦労した
- 自分の健康管理ができない:疲れやストレスにより、自分自身の体調を崩してしまう人も多かった
こうした状況が積み重なり、多くの保健師が「もう続けられない」と退職を決断するに至りました。
退職理由として多い要因とは
保健師が退職を考える理由にはさまざまな要因がありますが、特にコロナ禍では以下の要素が大きな影響を与えました。
- 業務量の急激な増加:通常業務に加え、コロナ対応の負担が増えた
- 精神的なストレス:感染拡大によるプレッシャーやクレーム対応に苦しんだ
- 人員不足による負担:退職者が増え、残った人に業務が集中した
- プライベートの犠牲:家族との時間が取れず、ワークライフバランスが崩れた
- 職場のサポート不足:上司や自治体からの支援が十分でなかった
このような理由が重なり、多くの保健師が退職を決断しています。
自治体や職場の対応と支援の実態
保健師の退職が相次ぐ中、自治体や職場でも対応策が求められました。
しかし、現実には十分な支援が行われなかったケースが多いのが実情です。
自治体や職場が実施した主な対応策には、以下のようなものがあります。
- 一時的な人員補充:臨時職員や派遣の活用
- 業務の効率化:デジタル化を進め、手作業を減らす取り組み
- メンタルケアの強化:カウンセリング制度の導入
- 長時間労働の是正:シフトの見直しや業務削減
- 給与や手当の改善:一部の自治体で特別手当を支給
しかし、実際にはこれらの対応策が十分に機能せず、現場の負担はあまり軽減されなかったという声も多く聞かれます。
今後の保健師の働き方に求められる変化
保健師が持続可能な働き方を続けるためには、今後の働き方に大きな変化が求められます。
特に重要な改善点は以下の5つです。
- 人員増加:新規採用を増やし、現場の負担を減らす
- 業務の分業化:感染症対応と通常業務を分け、専門性を高める
- メンタルヘルスケアの充実:保健師自身の心のケアを重視する
- 働き方改革:テレワークの活用や業務時間の適正化
- 市民との関係改善:クレーム対応の負担を減らし、サポート体制を強化する
これらの対策を進めることで、保健師が安心して働ける環境を整えていく必要があります。
保健師が退職を考える主な理由
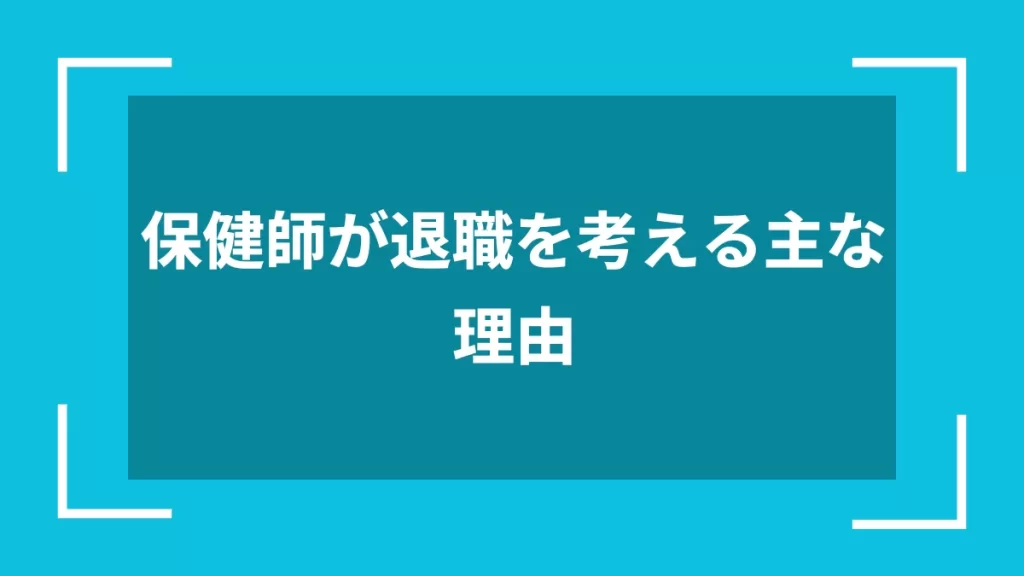
過重労働による身体的・精神的負担
保健師の退職理由の中で最も大きな要因のひとつが過重労働です。
コロナ禍では感染症対応に追われ、通常業務との両立が困難になりました。
その結果、身体的にも精神的にも大きな負担がかかり、多くの保健師が限界を迎えました。
特に、以下のような理由で疲労が蓄積しました。
- 長時間労働が続いた:休日返上や残業が常態化し、休む時間がなかった
- 肉体的な負担が大きかった:防護服を着用しながらの業務が長時間続いた
- 業務量が急激に増えた:通常の健康相談に加え、感染者対応が増加
- 責任が重かった:命に関わる判断を求められる場面が多かった
- 精神的なストレスが強かった:感染リスクやクレーム対応に疲れた
これらの要因が積み重なり、退職を決意する保健師が増えました。
職場環境や人間関係の問題
退職を考えるきっかけとして職場環境や人間関係の問題も深刻です。
どんなに仕事が好きでも、職場の人間関係が悪いと働き続けるのが難しくなります。
特に以下のようなケースが原因となることが多いです。
- 上司のサポートが不足:過酷な勤務状況でも適切な支援がなかった
- 同僚との協力体制が不十分:人手不足で業務を一人で抱え込むことが多かった
- パワーハラスメントの存在:厳しい指導や不適切な対応があった
- コミュニケーション不足:情報共有がうまくいかず、ミスにつながることがあった
- 職場の雰囲気が悪化:ストレスの多い環境で、ピリピリした空気が続いた
このような職場環境では、仕事のやりがいを感じることが難しくなり、退職を考える保健師が増えてしまいます。
キャリアの停滞とスキルアップの難しさ
保健師の仕事は専門的な知識やスキルを必要とする職業ですが、キャリアアップの道が限られていることも退職の理由のひとつです。
特に以下のような点に悩む人が多いです。
- 昇進の機会が少ない:管理職のポストが限られており、キャリアアップが難しい
- スキルを活かせる場が少ない:保健師の役割が固定され、新しいことに挑戦しにくい
- 専門知識の更新が大変:日々の業務に追われ、勉強の時間が取れない
- 同じ業務の繰り返し:新しい業務に挑戦できず、やりがいを感じにくい
- 転職しにくい:保健師の資格を活かせる職場が限られている
こうした状況が続くと、「このままでいいのか?」と将来に不安を感じ、転職を考える保健師が増えていきます。
ワークライフバランスの崩れ
保健師の仕事は社会的に重要な役割を担っていますが、その分、プライベートとのバランスが取りにくいことが課題となっています。
特にコロナ禍では、業務が増加し、ワークライフバランスが大きく崩れてしまいました。
以下のような理由で、仕事と生活の両立が難しくなっています。
- 残業が多く帰宅が遅い:家族との時間が取れない
- 休日でも緊急対応がある:完全に休める日が少ない
- ストレスが溜まりやすい:仕事の疲れが抜けず、リフレッシュできない
- 健康管理が難しい:自分の体調を気にする余裕がない
- プライベートの予定が立てにくい:急な呼び出しや残業で予定が崩れる
このような状況では、長く働き続けるのが難しくなり、退職を考える保健師が増えています。
待遇や給与への不満
保健師の仕事は責任が重く、専門的な知識やスキルが必要ですが、その割に給与や待遇が見合っていないと感じる人も多いです。
特に以下のような点に不満を持つ人が多くいます。
- 基本給が低い:民間企業と比べて給与が少ない
- ボーナスが少ない:公務員でも特別手当が少なく、収入に満足できない
- 昇給の機会が少ない:勤続年数が長くても給与が大きく変わらない
- 夜勤手当がない:長時間働いても手当がつかないことが多い
- 福利厚生が不十分:住宅手当や通勤手当が十分でない
このような待遇の問題も、退職を決意する大きな要因となっています。
退職を決意する前に考えるべきこと
退職を考える前に、もう一度自分の状況を整理し、本当に辞めるべきかを見極めることが大切です。
特に以下の点を考えることで、後悔しない決断ができます。
- 本当に辞めるべき理由があるか:感情的な判断ではなく、冷静に考える
- 転職先が決まっているか:次の仕事が決まる前に辞めるのはリスクがある
- 収入面で問題はないか:貯金や退職後の生活費を計算する
- 職場で解決できる問題はないか:異動や業務改善を求めることも選択肢
- 将来のキャリアを考えているか:退職後のビジョンを明確にする
これらをしっかり考えた上で、本当に必要なら新たな一歩を踏み出すことが大切です。
保健師の転職先とキャリアの選択肢
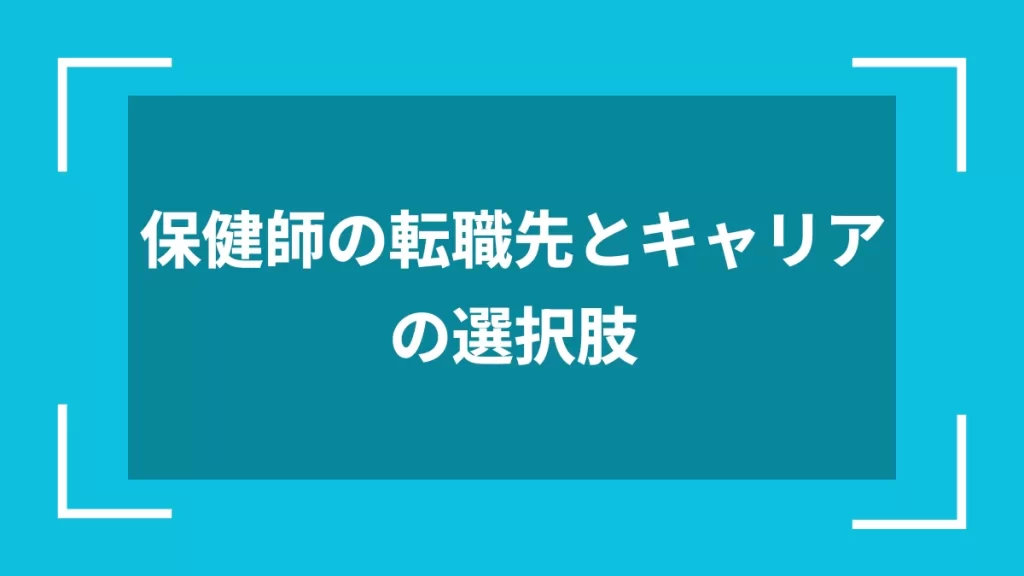
病院やクリニックへの転職
保健師が転職先として選ぶことが多いのが病院やクリニックです。
これまでの経験を活かしながら、より患者に近い環境で働くことができます。
特に以下のような理由で病院やクリニックへの転職を考える人が多いです。
- 患者との関わりが深い:地域保健よりも直接的な健康管理ができる
- 専門分野を活かせる:感染症管理や健康指導の経験が役立つ
- 夜勤がある職場も選べる:収入アップを目指せる
- チーム医療に携われる:医師や看護師と協力して働ける
- 待遇が良いことが多い:福利厚生が充実している病院もある
このように、病院やクリニックへの転職は、保健師の知識やスキルを存分に活かせる選択肢のひとつです。
企業保健師としてのキャリア
保健師の転職先として人気が高まっているのが企業保健師です。
企業内で従業員の健康管理を担当する仕事で、働きやすさや待遇の面で魅力が多い職場です。
企業保健師の主な業務は以下のようなものです。
- 健康診断の管理:従業員の健康診断を計画・実施する
- メンタルヘルスケア:ストレスチェックや相談対応を行う
- 健康教育の実施:社員向けの健康セミナーを企画する
- 労働環境の改善:過重労働の防止や職場環境の調整を行う
- 応急処置や医療相談:従業員の体調不良時の対応を行う
企業保健師は、夜勤がなくワークライフバランスが取りやすい点が大きな魅力です。
そのため、特に家庭と仕事を両立させたい人にとっては理想的な転職先となるでしょう。
自治体や行政機関での再就職
保健師としてのキャリアを活かしながら、行政機関で再就職する選択肢もあります。
自治体の保健所や福祉関連の部署では、コロナ禍以降、保健師の役割がますます重要になっています。
自治体や行政機関で働く保健師の主な業務は以下の通りです。
- 地域住民の健康相談:高齢者や子どもを対象にした健康指導
- 感染症対策:地域内の感染症予防施策の立案と実施
- 母子保健事業:妊婦や乳幼児の健康支援
- 生活習慣病予防:健康増進プログラムの企画・運営
- 災害時の保健活動:避難所での健康管理や支援活動
自治体の保健師は、住民と深く関わる仕事が多く、やりがいを感じやすい職場です。
また、公務員として安定した収入が得られる点もメリットとなります。
フリーランスや個人事業主としての働き方
近年では、保健師として独立して働く選択肢も注目されています。
企業や自治体に雇われるのではなく、自分自身で健康相談や研修講師の仕事を請け負うことが可能です。
フリーランス保健師の主な活動内容は以下の通りです。
- 健康相談サービスの提供:オンラインや対面で個別相談を実施
- 企業向けの健康研修:企業に出向き、健康指導の講義を行う
- 執筆活動:健康や医療に関する記事を執筆する
- YouTubeやSNSでの情報発信:動画や投稿を通じて健康情報を届ける
- オンライン講座の運営:健康管理やセルフケアに関する講座を開く
フリーランス保健師は自由な働き方ができる一方で、仕事を自分で見つける必要があります。
そのため、営業力や発信力が求められる点に注意が必要です。
保健師資格を活かせる異業種への転職
保健師の資格や経験を活かして、異業種に転職する道もあります。
医療や健康分野に関する知識を持っているため、さまざまな職種で活躍できる可能性があります。
保健師が活躍できる異業種の例を紹介します。
- 健康系のライター:医療や健康情報を発信する記事を書く
- 医療機器メーカーの営業:医療従事者向けの製品を提案する
- 健康食品やサプリメントの開発:成分や効果を調査し、商品開発に関わる
- スポーツジムやフィットネス業界:健康指導や栄養アドバイスを行う
- 医療系のカウンセラー:心理カウンセリングや健康相談を担当する
異業種転職は、新しい挑戦ができる反面、保健師の業務とは異なるスキルが求められることもあるため、慎重に選ぶことが大切です。
転職活動を成功させるポイント
保健師が転職を成功させるためには、しっかりとした準備が必要です。
特に以下のポイントを意識することで、より良い転職先を見つけやすくなります。
- 転職の目的を明確にする:なぜ転職したいのかを整理する
- 希望条件を具体的にする:給与、勤務地、業務内容などを考える
- 資格やスキルを活かせる仕事を選ぶ:これまでの経験が活かせる職場を探す
- 転職エージェントを活用する:保健師向けの求人を紹介してもらう
- 履歴書や面接対策をしっかり行う:自己PRや志望動機を明確にする
転職活動を成功させるためには、焦らずじっくりと準備を進めることが大切です。
自分に合った職場を見つけることで、充実したキャリアを築くことができるでしょう。
コロナ禍で退職する保健師が知っておくべきこと
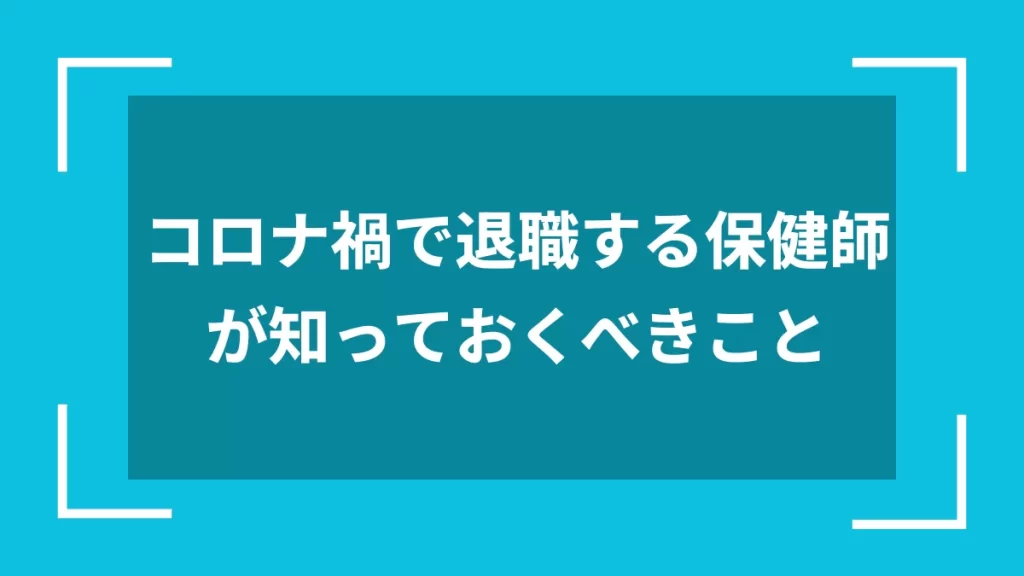
退職前に確認すべき手続きと注意点
保健師が退職を決意した際には、退職手続きや必要な準備をしっかり行うことが重要です。
特に以下の点を確認しておくと、スムーズに退職できます。
- 退職願・退職届の提出:職場の規定に従い、提出期限を守る
- 有給休暇の消化:退職前に取得できるかを確認する
- 健康保険の切り替え:国民健康保険か次の職場の保険に加入する
- 年金の手続き:厚生年金から国民年金に変更が必要な場合がある
- 退職金の確認:勤務年数に応じて受け取れるかを確認する
これらの手続きを忘れると、退職後の生活に影響が出る可能性があるため、しっかり準備をしておきましょう。
失業保険や各種支援制度の活用方法
保健師が退職後に利用できる支援制度はいくつかあります。
特に、失業保険は次の仕事が決まるまでの生活を支える重要な制度です。
失業保険を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 雇用保険に加入していた:退職前に雇用保険に加入していること
- 自己都合退職でも一定期間の勤務がある:1年以上勤務していた場合、受給可能
- ハローワークで求職活動を行う:定期的な求職活動が必要
また、失業保険のほかにも以下の支援制度が利用できます。
- 職業訓練受講給付金:新しいスキルを学ぶための支援金
- 再就職手当:早期に再就職した場合に支給される手当
- 生活福祉資金貸付制度:経済的に困ったときに利用できる支援
これらの制度を活用することで、退職後の負担を減らしながら次のステップに進みやすくなります。
転職活動をスムーズに進めるコツ
退職後の転職活動をスムーズに進めるためには、計画的に準備することが大切です。
特に以下のポイントを意識すると、希望に合った職場を見つけやすくなります。
- 退職前に転職活動を始める:在職中に求人情報をチェックする
- 保健師向けの転職サイトを活用する:専門の求人が多く掲載されている
- 履歴書と職務経歴書をしっかり準備する:自分の経験やスキルを明確に伝える
- 面接対策を行う:よく聞かれる質問に対する答えを準備する
- 自分の希望条件を整理する:給与、勤務地、業務内容などを明確にする
転職活動は焦らず慎重に進めることで、より良い環境で働くことができます。
退職後のキャリアプランを考える
退職後のキャリアを考える際には、長期的な目標を持つことが大切です。
保健師としての経験を活かし、どのような道を選ぶのかを決めることで、後悔のないキャリアを築くことができます。
主なキャリアプランの選択肢は以下の通りです。
- 病院やクリニックでの再就職:より臨床に近い環境で働く
- 企業保健師としての転職:ワークライフバランスを重視できる
- 自治体や行政機関での仕事:地域保健に携わる
- 異業種への転職:保健師の知識を活かして新しい分野に挑戦
- フリーランスとして独立:健康相談や執筆活動で働く
自分に合ったキャリアを選ぶことで、充実した働き方を実現できます。
心身の健康を維持しながら次のステップへ
退職後は心身の健康を整えることが何よりも大切です。
仕事を辞めた後に無理をすると、次の職場での適応が難しくなることもあります。
健康を維持するために意識すべきポイントは以下の通りです。
- しっかり休息を取る:心と体を回復させる時間を作る
- 生活リズムを整える:規則正しい生活を意識する
- 適度な運動をする:ストレス解消と体力維持に役立つ
- 人との交流を大切にする:孤独を感じないようにする
- 次のキャリアについて前向きに考える:焦らず自分のペースで準備する
心と体が健康であれば、新しい職場でもスムーズに働き始めることができます。
保健師としての経験を活かす新しい働き方
保健師の経験を活かして、新しい働き方に挑戦することも可能です。
特に以下のような働き方が注目されています。
- オンライン健康相談:インターネットを活用して健康アドバイスを行う
- ヘルスケア関連のライター:健康に関する記事を執筆する
- 研修講師:企業や自治体で健康指導の講師を務める
- YouTubeやSNSで情報発信:健康に関する知識を広める
- フリーランス保健師:自分のペースで働く
これらの働き方は、自由度が高く、ライフスタイルに合わせやすいのが特徴です。
自分に合ったスタイルを見つけることで、より充実したキャリアを築くことができます。
まとめ
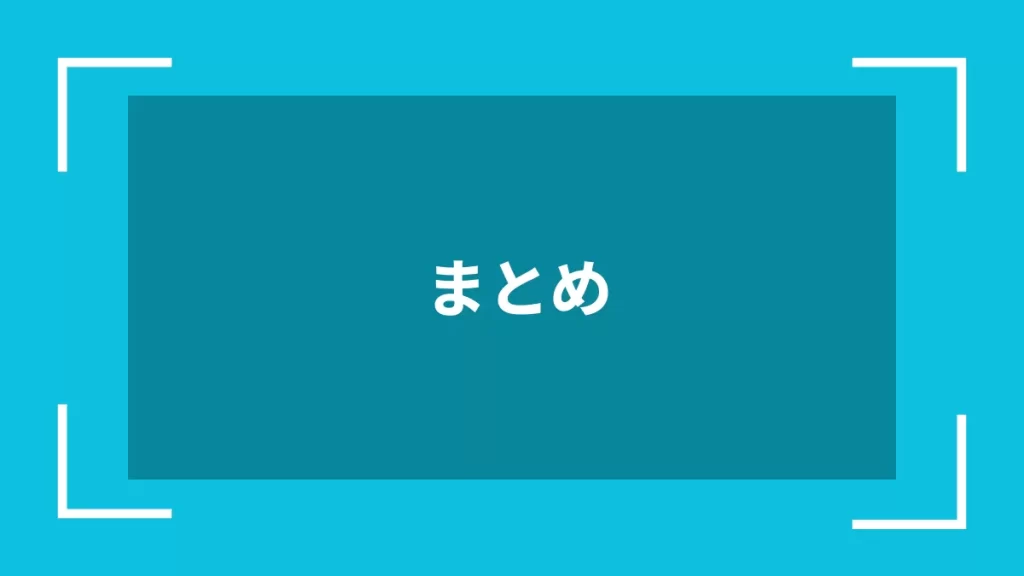
コロナ禍における保健師の退職事情と転職のポイントについて解説しました。
最後に、特に重要なポイントを振り返ります。
- コロナ禍で保健師の業務負担が急増:過重労働や精神的ストレスが原因で退職者が増えた
- 職場環境や待遇に不満を感じる人が多い:ワークライフバランスが崩れ、転職を考える保健師が増加
- 転職先の選択肢は豊富:病院、企業保健師、行政、フリーランスなど多様な道がある
- 退職前に手続きを確認する:健康保険や年金、失業保険などの制度をしっかり活用
- 転職活動は計画的に:転職サイトやエージェントを活用し、希望に合った職場を見つける
- 心身の健康を最優先に:退職後は十分に休み、新しい働き方を前向きに考える
保健師としての経験を活かしながら、自分に合った働き方を見つけることが大切です。
これからのキャリアをしっかり考え、一歩ずつ前に進んでいきましょう。







