新人保健師として働き始めたものの、「仕事がつらい」「思っていたのと違う」「辞めたい」と感じることはありませんか?
保健師の仕事はやりがいがある一方で、責任の重さや人間関係、業務の忙しさに悩む人も多いです。
特に新人のうちは慣れないことが多く、不安を抱えるのは当然のことです。
今回は、新人保健師が辞める前に知っておくべきことについて解説します。
辞めるかどうか迷っている方に向けて、仕事を続けるための対策や、辞める前に考えるべきポイントを詳しくお伝えします。
この記事を読めば、仕事を続ける方法や辞める際の準備が分かり、自分にとって最適な選択ができるようになります。
悩んでいる方は、ぜひ最後まで参考にしてください。
新人保健師が辞めたいと感じる主な理由
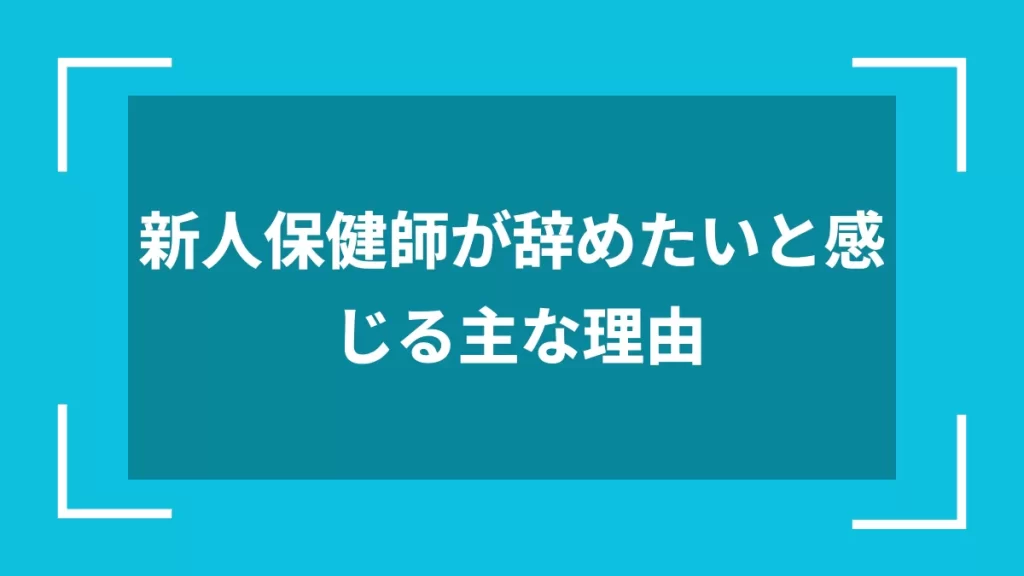
仕事のプレッシャーと責任の重さ
仕事のプレッシャーと責任の重さは、新人保健師が辞めたいと感じる大きな要因の一つです。
保健師は地域住民の健康を守る役割を担い、その判断や対応によって人の命に関わることもあります。
そのため、次のような点で強いプレッシャーを感じることが多いです。
- 健康相談の対応が難しい:専門知識が求められるため、正しい助言ができるか不安になる。
- ミスが許されない:誤った判断が住民の健康に影響を与える可能性があり、常に緊張感が伴う。
- 業務の幅が広い:母子保健、高齢者支援、生活習慣病予防など、幅広い分野に対応する必要がある。
- 責任が重い割にサポートが少ない:特に新人のうちは、適切なアドバイスを受ける機会が少なく、悩みを抱えやすい。
- 住民からの期待が大きい:地域住民から頼られる存在であるため、うまく対応できないと自己嫌悪に陥ることもある。
このように、保健師の仕事は責任が大きく、それがストレスになりやすいです。
しかし、適切な相談先を見つけたり、業務の進め方を工夫することで、プレッシャーを和らげることができます。
職場の人間関係に悩むことが多い
新人保健師の多くが、人間関係の悩みを抱えています。
保健師の職場は保健センターや行政機関が多く、上司や先輩との関係が仕事のやりやすさに大きく影響します。
特に以下のような点でストレスを感じることがあります。
- 指導が厳しすぎる:先輩や上司が厳しく、ミスをすると強く指摘されることがある。
- 相談しにくい雰囲気:忙しい職場では、質問しづらく、一人で抱え込んでしまうことがある。
- 他職種との連携が難しい:医師や看護師、行政職員などと連携する必要があり、意見が合わないこともある。
- 孤立しやすい:新人のうちは信頼関係が築けておらず、孤独を感じることがある。
- パワハラやモラハラの問題:職場によっては、厳しい上下関係があり、ストレスの原因になることもある。
職場の人間関係が悪いと、仕事のやる気も失われやすくなります。
しかし、信頼できる同僚を見つけたり、適切な距離感を保つことで、ストレスを軽減できることもあります。
理想と現実のギャップに戸惑う
保健師を目指していたときに描いていた理想と、実際の仕事の現実にギャップを感じることも、辞めたい理由の一つです。
特に以下のような点で戸惑うことが多いです。
- 想像以上に事務作業が多い:住民の健康相談や指導だけでなく、報告書作成やデータ入力などの事務作業が多い。
- 直接的な感謝を得にくい:病院の看護師と違い、成果がすぐに見えにくく、やりがいを感じにくいことがある。
- 住民対応が予想以上に大変:健康に関する相談だけでなく、生活や家族の悩みまで話されることがあり、対応が難しい。
- 政策や制度の変更に振り回される:行政の仕事なので、法律や方針の変更により、業務内容が大きく変わることがある。
- 想像していたよりも忙しい:イベントや講習会の準備、訪問活動などでスケジュールが埋まり、休憩を取る暇がないこともある。
理想と現実のギャップを感じることは、どんな仕事にもあります。
しかし、実際の業務の中で小さなやりがいを見つけたり、スキルを磨くことで、徐々に適応することが可能です。
業務の忙しさや残業の多さ
保健師の仕事は意外と忙しく、残業が多くなることもあります。
特に新人のうちは仕事に慣れていないため、業務をスムーズに進められず、時間がかかることが多いです。
以下のような点で負担を感じることがよくあります。
- イベントや講習会の準備が多い:健康教室や講演会の企画・運営などがあり、準備に時間がかかる。
- 訪問活動で時間が取られる:家庭訪問や高齢者支援などで外出が多く、戻ってからの事務作業が大変になる。
- 緊急対応が発生する:感染症の発生や災害時の対応など、急な仕事が入ることがある。
- 定時で帰れないことが多い:会議や報告書作成があるため、残業せざるを得ないことがある。
- 一人で抱え込む業務が多い:担当する業務が決まっているため、自分だけが忙しくなることがある。
仕事が忙しすぎると、心身ともに疲れやすくなります。
しかし、優先順位をつけて業務を進めたり、無理のないスケジュールを意識することで、少しずつ負担を減らすことができます。
メンタル面での負担が大きい
新人保健師は、精神的な負担を感じることが多いです。
業務のプレッシャーや人間関係、仕事の忙しさなどが重なり、心の余裕をなくしてしまうことがあります。
特に以下のような点でストレスを感じやすいです。
- 常に正しい判断を求められる:健康に関する助言をするため、間違いが許されないプレッシャーがある。
- 住民との関係が難しい:対応がうまくいかないと、クレームを受けることもある。
- 相談できる相手が少ない:職場に気軽に相談できる人がいないと、悩みを抱え込んでしまう。
- 自信を失いやすい:新人のうちはミスが多く、自己肯定感が下がることがある。
- ストレス発散の時間が取れない:忙しくてリフレッシュする時間がなく、疲れが溜まりやすい。
メンタルの負担が大きいと、仕事のモチベーションも下がってしまいます。
しかし、適度に休憩を取ったり、ストレス解消法を見つけることで、少しずつ心の負担を減らすことができます。
辞める前に考えるべきポイント
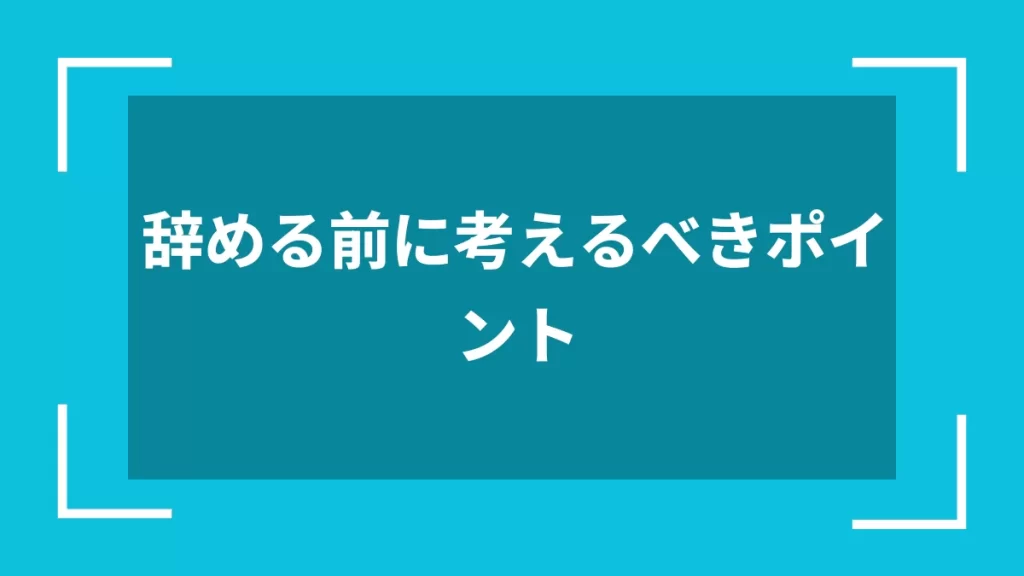
本当に辞めるべきか冷静に判断する方法
辞めたいと感じたときは、まず冷静になり、本当に辞めるべきかを判断することが大切です。
感情的に決めてしまうと、後で後悔することもあります。
次のポイントを意識して、慎重に考えましょう。
- 辞めたい理由を明確にする:仕事の何がつらいのか具体的に書き出す。
- 一時的な感情かどうか確認する:忙しさやミスによる一時的なストレスではないか見極める。
- 解決策がないか考える:業務のやり方を工夫すれば負担が減るかもしれない。
- 他の人に相談する:家族や先輩に話すことで、自分の気持ちを整理できる。
- 辞めた後のリスクを把握する:次の仕事が決まっていない場合、生活に影響が出る可能性がある。
このように、感情だけで判断せず、冷静に考えることで、本当に辞めるべきかどうかが見えてきます。
仕事の悩みを相談できる相手を見つける
仕事の悩みを一人で抱え込むと、精神的な負担が大きくなります。
適切な相談相手を見つけることで、気持ちが楽になり、解決策が見つかることもあります。
相談できる相手として、次のような人が考えられます。
- 先輩や上司:職場の事情を理解しているため、具体的なアドバイスをもらえる。
- 同僚や同期:同じ立場の人と話すことで、共感を得られ気持ちが軽くなる。
- 家族や友人:仕事以外の視点から意見をもらえ、冷静に考えられる。
- 専門の相談窓口:保健師向けの相談サービスやメンタルヘルスの専門機関を活用する。
- キャリアアドバイザー:転職も視野に入れる場合、専門家に相談すると役立つ情報を得られる。
相談することで、自分では気づかなかった解決策が見つかることもあります。
一人で悩まず、信頼できる人に話してみましょう。
環境を変えることで解決できる可能性
辞めたいと感じる理由が、職場の環境にある場合は、仕事を続けながら環境を変える方法を考えるのも一つの手です。
環境を変えることで、状況が改善されることがあります。
- 業務の進め方を工夫する:時間の使い方を見直し、負担を減らす。
- 苦手な人との距離を取る:無理に関わろうとせず、適度な距離を保つ。
- 配置転換を相談する:異動の希望を出せば、新しい環境でやり直せることもある。
- ストレス発散の時間を作る:趣味や運動でリフレッシュし、気持ちを切り替える。
- 短期間の休みを取る:心身ともにリフレッシュすれば、冷静に判断できる。
職場環境を変えるだけで、辞めたい気持ちが和らぐことがあります。
すぐに辞める前に、できることを試してみましょう。
辞めた後のキャリアプランを考える
辞める決断をする前に、辞めた後のキャリアについてもしっかり考えておくことが大切です。
計画を立てずに辞めると、次の仕事が決まらず、焦ることになりかねません。
以下の点を意識して、キャリアプランを考えましょう。
- 転職の可能性を調べる:他の保健師の求人や、関連する職種の選択肢を調べる。
- スキルアップの方法を考える:新しい資格を取る、専門知識を深めるなど、次の仕事に活かせる準備をする。
- 働き方を見直す:正社員にこだわらず、非常勤やフリーランスの道も検討する。
- 収入の安定を考慮する:辞めた後すぐに収入が途絶えないよう、貯金や副業などの準備をする。
- やりたい仕事を明確にする:本当にやりたい仕事が何なのか、一度じっくり考えてみる。
しっかりとキャリアプランを考えることで、不安を減らし、安心して次のステップに進めます。
休職という選択肢も検討する
辞めたいと感じたとき、すぐに退職するのではなく、休職という選択肢を考えるのも一つの方法です。
一定期間休むことで、心身を回復させ、冷静に今後を考えることができます。
- 心の余裕を取り戻せる:仕事から離れることで、冷静に自分の状況を見直せる。
- 職場復帰の可能性を残せる:辞めずに済むなら、これまで築いた人間関係やキャリアを活かせる。
- 健康を守ることができる:ストレスが原因で体調を崩している場合、無理をせず休むことが重要。
- 経済的なリスクを減らせる:すぐに収入を失うわけではないため、生活の安定を保てる。
- 本当に辞めるべきかじっくり考えられる:休職中に、次のキャリアをゆっくり考える時間ができる。
休職を選ぶことで、気持ちに余裕が生まれ、今後の選択肢を広げることができます。
いきなり辞めるのではなく、まずは休むことも検討してみましょう。
新人保健師が働きやすくなるための対策
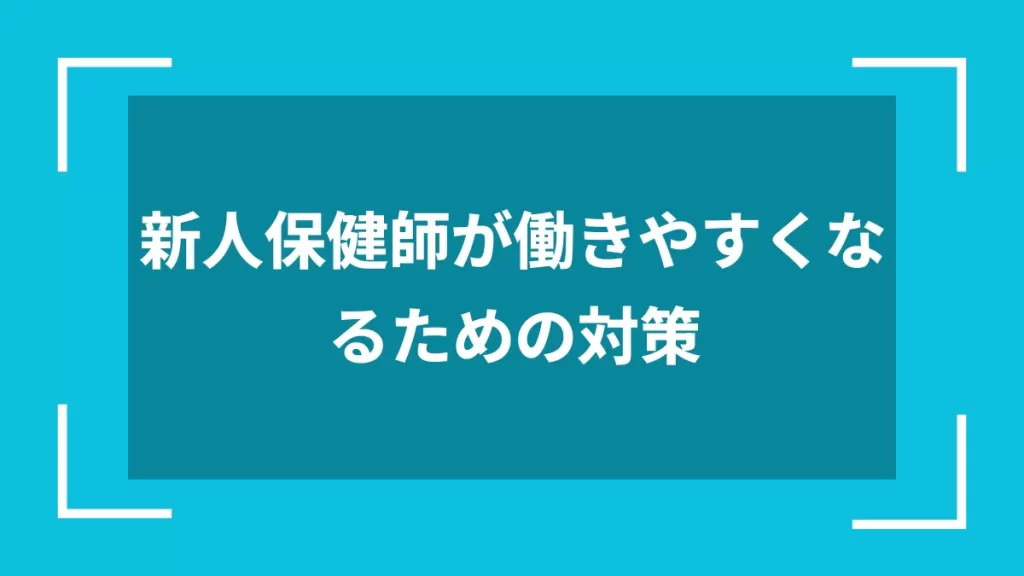
仕事の進め方を工夫する
仕事の進め方を見直すことで、業務の負担を減らし、よりスムーズに働くことができます。
特に新人のうちは、効率よく業務をこなすことが難しく、時間がかかることが多いです。
以下のような工夫をすることで、仕事を進めやすくなります。
- 業務の優先順位をつける:重要な仕事から取り組み、後回しにできるものは計画的に進める。
- メモを活用する:教わったことをノートにまとめ、何度も確認できるようにする。
- スケジュール管理を徹底する:1日の流れを整理し、無駄な時間を減らす。
- 分からないことはすぐに聞く:悩んで時間を無駄にするよりも、早めに確認して解決する。
- 書類作業を効率化する:テンプレートを作成する、PCのショートカットを活用するなど工夫する。
仕事の進め方を工夫することで、ストレスが減り、余裕を持って働けるようになります。
ストレスを軽減する方法を取り入れる
ストレスを減らすことで、仕事の負担感が和らぎ、辞めたい気持ちを軽減できます。
特に保健師の仕事は精神的な負担が大きいため、日頃からストレス対策を意識することが重要です。
- こまめに休憩を取る:短時間でも席を離れたり、深呼吸することで気持ちをリフレッシュできる。
- 適度な運動をする:ウォーキングやストレッチをすることで、気分がスッキリする。
- 趣味の時間を確保する:好きなことをすることで、仕事のストレスを忘れられる。
- 同僚と悩みを共有する:同じ立場の人と話すことで、共感を得て気持ちが軽くなる。
- 仕事とプライベートを切り替える:仕事が終わったらリラックスできる環境を作る。
ストレスをうまく発散することで、心身の負担が減り、仕事を続けやすくなります。
先輩や上司との関係を良好にするコツ
職場の人間関係が良好だと、仕事のしやすさが大きく変わります。
特に新人のうちは、先輩や上司とうまく付き合うことが大切です。
関係を良くするために、次のようなポイントを意識しましょう。
- 挨拶をしっかりする:毎日の挨拶を丁寧にすることで、印象が良くなる。
- 報告・連絡・相談を徹底する:仕事の進捗をこまめに伝えることで、信頼関係が築ける。
- 感謝の気持ちを伝える:教えてもらったら「ありがとうございます」としっかり伝える。
- 謙虚な姿勢を持つ:分からないことを素直に聞き、学ぶ姿勢を大切にする。
- 無理に馴れ合わない:親しくなることは大事だが、距離感を大切にすることでトラブルを防げる。
先輩や上司とうまく関係を築くことで、仕事がスムーズに進み、働きやすくなります。
同僚や同期と悩みを共有する
同じ立場の人と悩みを共有することで、不安が和らぎ、精神的な支えになります。
特に新人のうちは、孤独を感じやすいですが、周囲とコミュニケーションを取ることで安心感を得られます。
- 仕事の愚痴を言い合う:無理に我慢せず、適度に発散することが大切。
- 情報を共有する:仕事のコツや経験を共有し、お互いに成長する。
- 励まし合う:辛いときに「自分だけじゃない」と思えると気持ちが楽になる。
- 定期的に交流の機会を作る:食事やお茶をすることで、仕事以外の話もしやすくなる。
- 競争ではなく協力する:比較せず、お互いをサポートすることで職場の雰囲気が良くなる。
同僚と支え合うことで、仕事のストレスが減り、前向きに働くことができます。
専門的な知識やスキルを身につける
スキルアップをすることで、自信がつき、仕事の負担が減ります。
保健師としての知識を増やすことで、業務をスムーズにこなせるようになり、不安を感じにくくなります。
- 研修や勉強会に参加する:最新の情報を学び、知識を深める。
- 医療・福祉関連の書籍を読む:専門書を読むことで、業務に活かせる知識が増える。
- 先輩の仕事を観察する:経験豊富な保健師の働き方を学び、参考にする。
- 実践を通じてスキルを磨く:実際の業務をこなしながら、経験を積むことが大切。
- 自分に合った学び方を見つける:オンライン講座や動画を活用するのも効果的。
知識を増やし、スキルを高めることで、仕事に対する不安を減らし、やりがいを感じられるようになります。
辞める決断をした後にすべきこと
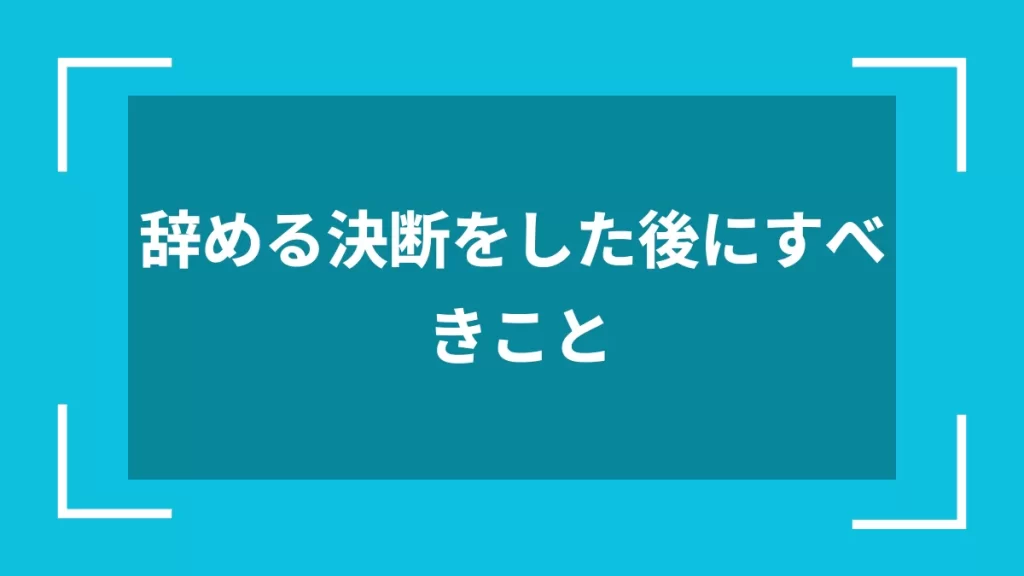
退職までのスケジュールを立てる
辞めることを決めたら、スムーズに退職できるようスケジュールを立てることが大切です。
突然辞めると、職場や周囲に迷惑がかかるため、計画的に進めましょう。
- 退職希望日の設定:退職のタイミングを考え、繁忙期を避ける。
- 上司への報告:まず直属の上司に相談し、退職の意思を伝える。
- 退職願の提出:正式な書類を準備し、必要な手続きを進める。
- 引き継ぎの準備:後任者が困らないよう、業務内容を整理する。
- 最終出勤日の確認:有給消化の計画も考え、最終出勤日を決める。
計画を立てることで、円満に退職でき、次のステップへ安心して進めます。
円満退職に向けた準備をする
退職を決めたら、円満に辞められるように準備をすることが重要です。
トラブルなく退職するために、以下の点に注意しましょう。
- 早めに上司に相談する:できるだけ早く伝えることで、職場の混乱を防ぐ。
- 感謝の気持ちを伝える:お世話になった職場の人に、しっかりお礼を言う。
- ネガティブな発言を控える:職場の不満を言わず、前向きな理由で退職する。
- 業務の引き継ぎを丁寧に行う:次の人がスムーズに仕事を続けられるように準備する。
- 最終日まで誠実に働く:最後まで手を抜かず、良い印象を残す。
円満退職を心掛けることで、辞めた後も良い関係を維持でき、次の仕事にも良い影響を与えます。
転職活動をスムーズに進める方法
退職を決めたら、次の仕事を見つけるための転職活動を進める必要があります。
効率よく転職先を探すために、次のポイントを意識しましょう。
- 転職の目的を明確にする:何を改善したいのか、どんな働き方をしたいのかを整理する。
- 求人情報をリサーチする:保健師の求人サイトや転職エージェントを活用する。
- 履歴書・職務経歴書を準備する:応募に必要な書類を整え、分かりやすくまとめる。
- 面接対策をする:よく聞かれる質問を事前に考え、スムーズに答えられるようにする。
- 在職中に転職先を決める:次の仕事が決まる前に辞めると、収入が途絶えるため注意する。
転職活動を計画的に進めることで、スムーズに新しい仕事を見つけ、安心して次のステップに進めます。
退職後の生活をしっかり計画する
退職後の生活を計画しておかないと、収入や日々の過ごし方に困ることがあります。
次のような点を意識し、計画を立てましょう。
- 生活費の管理をする:収入が減る可能性があるため、無駄な支出を減らす。
- 健康保険と年金の手続きを確認する:退職後の手続きを忘れずに行う。
- 新しい仕事に向けて準備する:転職や再就職に必要なスキルを学ぶ。
- 休息の時間を確保する:無理に次の仕事を探すのではなく、少し休むことも大切。
- 趣味や自己成長の時間を作る:これまでできなかったことに挑戦する。
退職後の生活をしっかり考えておくことで、安心して次のステップへ進めます。
新しい環境でのスタートを前向きに考える
退職後、新しい環境でのスタートを前向きに考えることが大切です。
次の職場でうまくやるために、意識しておくべきことを整理しましょう。
- 新しい仕事に期待を持つ:過去の職場と比べるのではなく、新しい挑戦を楽しむ。
- 環境に慣れる努力をする:最初は戸惑うことも多いが、積極的に学ぶ姿勢を持つ。
- 人間関係を大切にする:新しい職場の人と良い関係を築くために、丁寧なコミュニケーションを心掛ける。
- 自分のペースを大切にする:無理に頑張りすぎず、徐々に慣れていく。
- ポジティブな気持ちを持つ:新しい環境は不安もあるが、前向きに考えることで良い方向に進む。
新しい環境でのスタートを前向きに考えることで、より良い仕事や人間関係を築くことができます。
まとめ

新人保健師が辞める前に考えておくべきことを整理しました。
大切なポイントをもう一度確認しましょう。
- 辞めたい理由を明確にする:一時的な感情なのか、本当に辞めるべきかを冷静に判断する。
- 相談できる相手を見つける:先輩や同僚、家族に話すことで気持ちを整理する。
- 仕事の進め方を工夫する:優先順位をつけ、効率よく業務を進める方法を試す。
- ストレスを軽減する方法を取り入れる:休憩や運動、趣味の時間を確保し、気持ちをリフレッシュする。
- 退職のスケジュールを計画的に立てる:引き継ぎや手続きを準備し、円満退職を心がける。
- 次のキャリアをしっかり考える:転職先を探したり、新しいスキルを身につけたりして、次のステップに備える。
辞める前にできることを試し、最善の選択をしましょう。
焦らず、自分にとって後悔しない決断をすることが大切です。







