仕事に慣れないうちから、「毎日が辛い」「このまま続けられる気がしない」と感じることもありますよね。
理想と現実のギャップ、職場の人間関係、仕事のプレッシャーなど、新卒の保健師が辞めたいと考える理由はさまざまです。
今回は、「新卒保健師が辞めたいと感じたときに考えるべきこと」について詳しく解説します。
辞めるべきか悩んでいる方に向けて、退職の判断基準や次のキャリアの選択肢、後悔しない退職方法まで紹介します。
この記事を読めば、「辞めるべきか続けるべきか」が整理でき、自分に合った選択ができるようになります。
悩んでいる今こそ、自分の未来についてしっかり考えるタイミングです。
ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
新卒保健師が辞めたいと感じる理由とは?
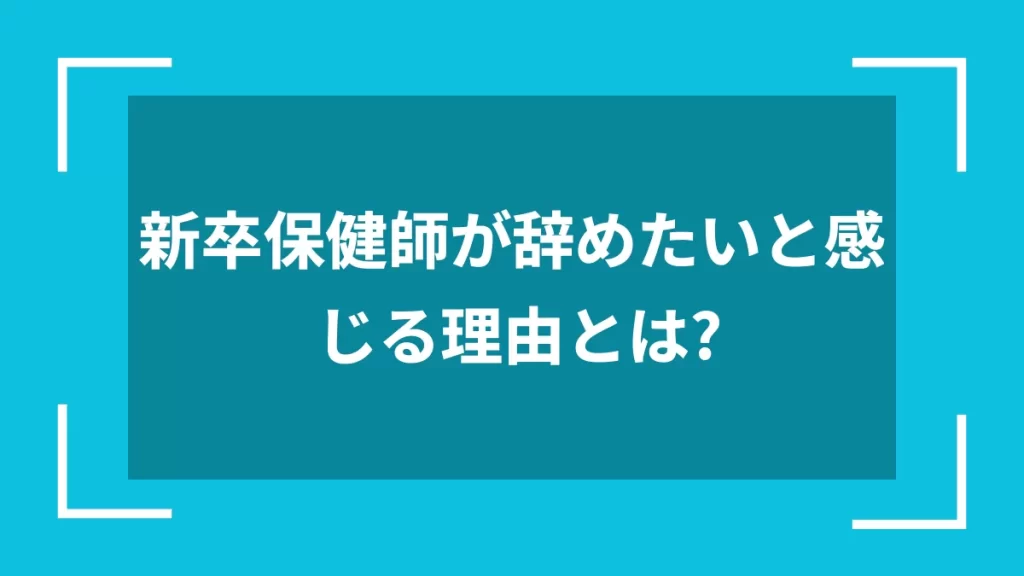
仕事のプレッシャーと精神的負担
仕事のプレッシャーや精神的負担は、新卒保健師が「辞めたい」と感じる大きな要因の一つです。
特に、医療や福祉の現場では、人の命や健康に関わる責任が非常に重いため、強いストレスを感じることがあります。
具体的には、以下のようなプレッシャーを抱えがちです。
- 業務量の多さ – 予防接種や健康相談、地域訪問など、業務が多岐にわたり、忙しさに追われる
- 判断ミスの不安 – 適切な対応を求められる場面が多く、「間違えてはいけない」というプレッシャーを感じる
- 患者や住民との関わり – クレーム対応や厳しい意見を受けることがあり、精神的に辛くなる
- 上司や先輩からの指導 – 指導が厳しい場合や、理不尽な注意を受けることがストレスになる
- 責任の重さ – 保健師のアドバイスが住民の健康に影響を与えるため、大きな責任を感じる
こうしたストレスが積み重なると、次第に「もう続けられない」「辞めたい」と感じてしまうことがあります。
しかし、適切なストレス対処法を身につけることで、精神的な負担を軽減することも可能です。
職場の人間関係の悩み
新卒保健師の多くが、職場の人間関係に悩みを抱えています。
特に、保健師の職場は女性が多いため、コミュニケーションの取り方が難しく感じることもあります。
人間関係の悩みとしては、次のようなものがあります。
- 上司や先輩が厳しい – ミスをすると強く指導されることが多く、萎縮してしまう
- 同僚との距離感 – 仕事の忙しさから、同僚と十分にコミュニケーションを取る機会が少ない
- 派閥がある – 職場にグループや派閥ができていて、なじめないことがある
- 相談しづらい環境 – 悩みがあっても、誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまう
- パワハラやいじめ – 指導を超えた厳しい対応を受けることがあり、精神的に追い詰められる
人間関係の悩みは、仕事のやる気にも大きく影響を与えます。
もし、悩みが深刻であれば、信頼できる人に相談したり、異動や転職を考えることも一つの選択肢です。
業務内容と理想のギャップ
新卒保健師の中には、「思っていた仕事と違う」と感じる人も多いです。
特に、学生時代にイメージしていた理想と現実のギャップが大きいと、モチベーションが下がってしまいます。
よくあるギャップには、以下のようなものがあります。
- デスクワークが多い – 現場での活動よりも、報告書や資料作成に追われることが多い
- 住民対応の難しさ – 相談に乗るだけでなく、クレーム処理なども仕事の一部
- チームワークより個人プレー – 相談業務や訪問活動は一人で行うことが多く、孤独を感じる
- 医療行為ができない – 看護師と違い、直接的な医療処置ができず、もどかしさを感じる
- 意見が通りにくい – 上司や自治体の方針に従う場面が多く、自分の考えが反映されにくい
このようなギャップがあると、「この仕事を続けていていいのか?」と不安になります。
しかし、仕事に慣れることで、やりがいや楽しさを感じることもあるため、一度冷静に現状を見直してみることも大切です。
給与や待遇への不満
新卒保健師の中には、給与や待遇に不満を感じる人も少なくありません。
特に、期待していた収入と現実の差が大きいと、モチベーションが下がる原因になります。
よくある不満点としては、以下のようなものがあります。
- 初任給が低い – 看護師と比べて、保健師の給与は高くない
- 昇給が少ない – 公務員の場合、昇給スピードが遅く、大幅な給与アップが見込めない
- 残業代がつかない – 役所勤務では、サービス残業が発生することもある
- ボーナスが期待以下 – 安定はしているが、一般企業と比べると低め
- 福利厚生に満足できない – 期待していた手当や支援制度が十分ではない
給与や待遇に不満がある場合は、転職を視野に入れるのも一つの手です。
特に、民間企業の保健師や一般企業へのキャリアチェンジを検討することで、より良い条件の仕事を見つけることができる可能性があります。
新卒保健師が辞めたいと感じた時に考えるべきこと
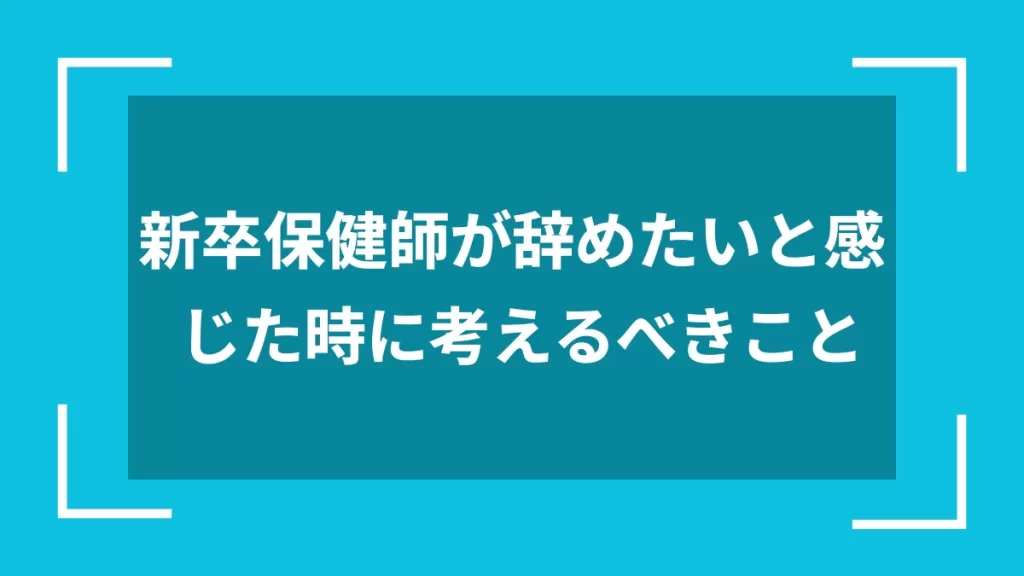
退職を決断する前に確認すべきポイント
新卒保健師が「辞めたい」と感じたとき、すぐに決断するのは危険です。
まずは、自分の状況を冷静に整理し、本当に退職するべきかどうかを考えましょう。
以下のポイントを確認することで、後悔のない判断ができます。
- 辞めたい理由が一時的なものか – 一時的なストレスや人間関係の問題が原因なら、時間が解決する可能性がある
- 他の選択肢はないか – 休職や部署異動など、退職以外の解決策があるかを検討する
- 辞めた後の生活設計はできているか – 経済的な準備や次の仕事が決まっていないと、後悔することもある
- 本当にやりたいことがあるか – 次のキャリアプランが明確でないと、転職しても同じ悩みに直面する可能性がある
- 相談できる人がいるか – 友人や先輩、キャリアカウンセラーなどに話を聞いてもらうことで、新しい視点が得られる
これらのポイントを確認した上で、それでも「辞めたい」という気持ちが強い場合は、次のキャリアについて考えることが大切です。
辞めた後のキャリアプランを考える
新卒で保健師を辞めた後のキャリアを考えずに退職すると、転職に苦労することがあります。
次のキャリアを考える際は、以下の点を意識しましょう。
- 保健師の資格を活かせる仕事を探す – 産業保健師や企業の健康管理部門など、資格が役立つ職場は多い
- 医療や福祉以外の道を考える – 一般企業の人事部やカウンセリング職など、別業界で活躍できる可能性がある
- スキルアップを視野に入れる – 新しい資格を取得したり、研修に参加することで、転職の選択肢が広がる
- 自分の適性を見極める – 仕事の内容だけでなく、自分の性格や価値観に合った職場を選ぶことが大切
- 長期的なキャリアビジョンを持つ – 目先のことだけでなく、5年後、10年後の自分をイメージして職を選ぶ
しっかりとキャリアプランを考えておけば、保健師を辞めた後も、充実した仕事人生を送ることができます。
転職と休職、どちらが適しているか
「辞めるか続けるか」の間には、「休職する」という選択肢もあります。
転職と休職のどちらが自分に合っているのか、比較してみましょう。
- 転職が向いている人
- 現在の仕事に強い不満がある
- 他にやりたい仕事が明確にある
- 精神的に限界を感じている
- 経済的に転職活動をする余裕がある
- 休職が向いている人
- 一時的なストレスや体調不良が原因
- 仕事内容は好きだが、環境が合わない
- 復職の可能性がある
- 会社に休職制度がある
どちらの選択をするにせよ、自分の心身の健康を第一に考えることが大切です。
周囲の意見と自分の気持ちのバランス
保健師を辞める決断をする際、周囲の意見を気にする人は多いです。
しかし、他人の意見に流されるだけでは後悔する可能性があります。
次のような考え方を大切にしましょう。
- 家族や友人の意見は参考にする – 客観的な意見を聞くことで、自分では気づけなかった点に気づくことができる
- 職場の人の意見はあくまで職場目線 – 「続けたほうがいい」と言われても、それが本当に自分にとって良いとは限らない
- 自分の気持ちを最優先にする – 最終的に決めるのは自分。自分がどうしたいのかを大切にする
- 後悔しない選択をする – 周囲の期待に応えるだけでなく、自分が納得できる決断をすることが重要
自分の人生を決めるのは自分です。
他人の意見も参考にしつつ、最も納得できる道を選びましょう。
退職後の生活設計と準備
退職を決断した場合、次の生活の準備をしっかり行うことが重要です。
無計画で辞めてしまうと、後で後悔することになりかねません。
- 貯金を確保する – すぐに転職できない可能性も考え、生活費を数か月分は確保しておく
- 退職後の手続きを把握する – 失業保険や健康保険の手続きを事前に調べておく
- 次の仕事を探し始める – 転職活動を先に進めておくと、スムーズに新しい職場へ移れる
- 必要なスキルを身につける – 転職のために、新しい資格やスキルを習得するのも有効
しっかり準備をしておけば、安心して新しいキャリアへ踏み出すことができます。
新卒保健師が次に選べるキャリアの選択肢
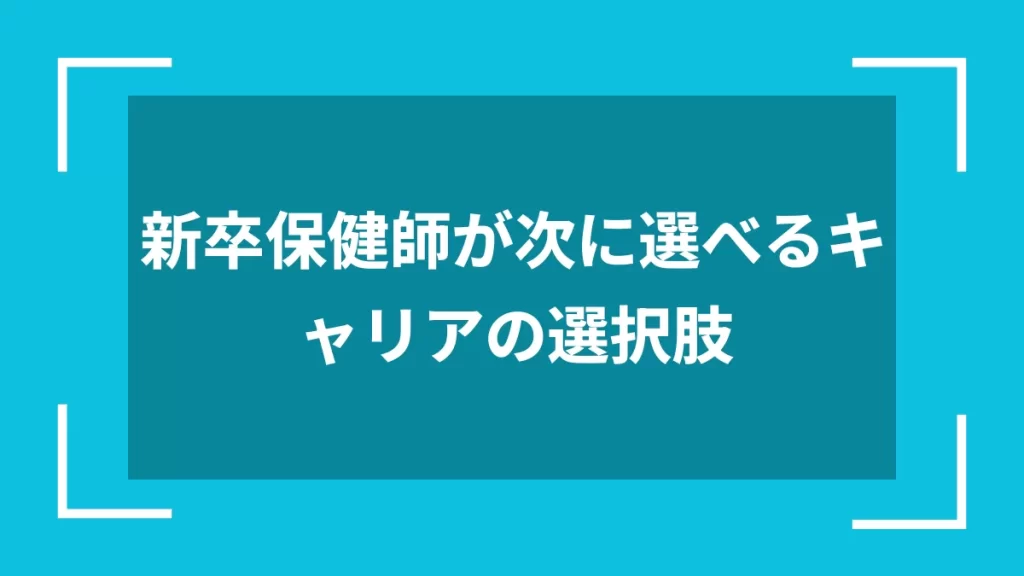
他の医療職への転職
保健師として働く中で「医療職に携わりたいが、今の仕事は合わない」と感じる人もいます。
そんな場合、他の医療職へ転職する選択肢があります。
保健師の資格や経験を活かせる仕事には、以下のようなものがあります。
- 看護師 – 医療現場で直接患者を支援できるため、より実践的な医療に関われる
- 助産師 – 妊産婦や新生児のケアに携わりたい人に向いている
- 臨床検査技師 – 医療機関で検査業務を担当し、診断に貢献できる
- 医療ソーシャルワーカー – 患者の社会的な支援を行い、福祉と医療の架け橋となる
これらの職種に転職する場合、追加の資格が必要なことが多いため、事前に資格取得のための計画を立てることが重要です。
一般企業へのキャリアチェンジ
保健師の仕事を辞める理由の一つに、「医療現場ではなく、一般企業で働きたい」という思いがあります。
保健師の経験を活かしながら、一般企業で働く方法もあります。
- 産業保健師 – 企業の従業員の健康管理を行い、労働環境の改善に貢献する
- 人事・労務担当 – 健康経営に関わる業務を行い、働きやすい職場づくりをサポートする
- カウンセラー – メンタルヘルスの専門家として、従業員の心のケアを行う
- 営業職 – 医療機器メーカーや製薬会社などで、医療知識を活かしながら働ける
一般企業での仕事は、保健師とは異なるスキルが求められるため、転職前に企業の仕事内容をよく調べることが大切です。
フリーランスや独立の道
保健師の仕事を辞めた後、フリーランスや独立を目指す人もいます。
自分のペースで働きたい、自由な働き方をしたいという場合には、次のような選択肢があります。
- 健康コンサルタント – 個人や企業向けに健康アドバイスを提供する
- オンラインカウンセリング – メンタルヘルスや健康相談の専門家として活動する
- 健康系ライター – 健康や医療に関する記事を執筆し、メディアで活躍する
- YouTuberやブロガー – 健康情報を発信し、フォロワーを増やすことで収益を得る
フリーランスや独立の道を選ぶ場合、収入が不安定になるリスクもあるため、事前に資金計画をしっかり立てることが必要です。
公務員や行政職への転職
保健師は、公務員として働くことが多いですが、より安定した仕事を求めて他の行政職に転職する人もいます。
公務員として働く場合、以下のような職種が考えられます。
- 市町村の行政職 – 地域住民の健康や福祉政策に関わる仕事
- 保健所職員 – 地域の健康管理を支援し、感染症対策などに携わる
- 厚生労働省職員 – 国の健康政策に関与し、保健医療制度の運営を担う
公務員試験を受ける必要がある職種もあるため、事前に試験対策をすることが重要です。
資格を活かした別業界での活躍
保健師の資格を活かして、医療や福祉以外の業界で働くことも可能です。
次のような分野では、保健師の知識が役立ちます。
- フィットネス業界 – 健康管理や運動指導の専門家として活躍する
- 食品・栄養関連 – 健康食品やサプリメントの開発や販売に関わる
- 教育分野 – 学校保健師や養護教諭として、学生の健康管理を行う
異業種で働く場合は、新たなスキルを身につけることで、より幅広い仕事にチャレンジできます。
再び保健師として働く道もある
一度は保健師を辞めたいと考えたものの、別の環境なら続けられるかもしれません。
職場を変えることで、働きやすい環境を見つけることができます。
- 自治体を変えて働く – 別の市町村の保健師として働くと、職場環境が大きく変わることがある
- 企業保健師に転職する – 産業保健師として企業で働くと、医療現場とは違ったやりがいを感じられる
- 病院やクリニックで勤務する – 医療機関で働くことで、保健師の経験を活かしながら新たなスキルを学べる
保健師の仕事を辞める前に、「働く場所を変えることで解決できる問題はないか」を考えてみるのも良い方法です。
新卒保健師が後悔しない退職をするために
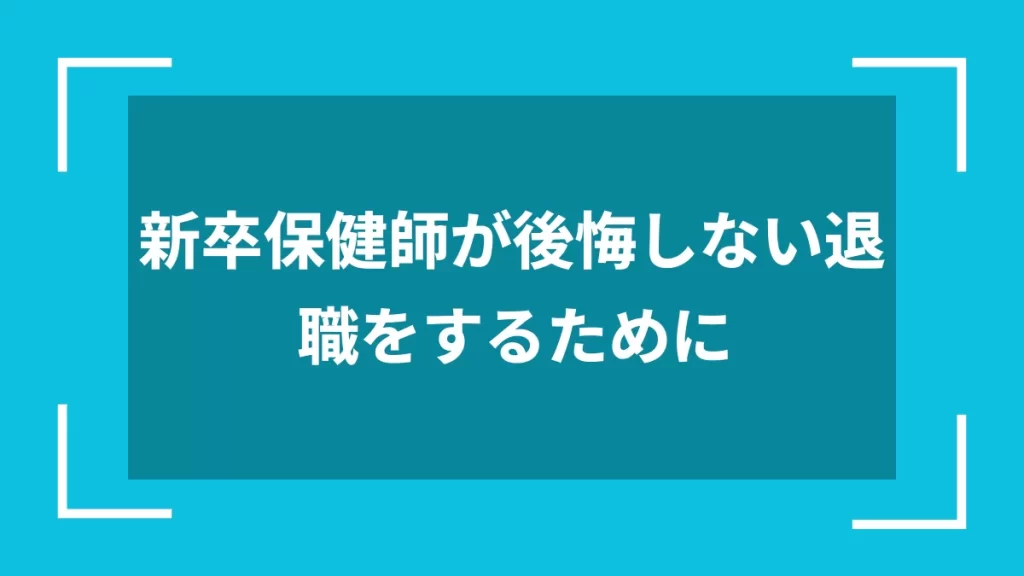
スムーズな退職の進め方
退職を決意したら、できるだけ円滑に手続きを進めることが大切です。
退職の流れを理解し、計画的に進めることで、トラブルを避けることができます。
以下の手順を参考にして、スムーズに退職しましょう。
- 退職の意思を固める – 転職先の準備や経済的な見通しを立てた上で、退職を決断する
- 上司に相談する – 退職の意向を早めに伝え、引き継ぎの計画を共有する
- 退職願を提出する – 退職日を決定し、正式な書類を提出する
- 引き継ぎを行う – 後任者に業務をしっかり引き継ぎ、迷惑をかけないようにする
- 退職後の手続きを確認する – 健康保険や年金の手続きを忘れずに行う
退職後に困らないよう、事前にしっかりと準備をしておくことが重要です。
円満退職のためのポイント
退職は個人の自由ですが、できるだけ円満に進めることが大切です。
職場との関係を良好に保ちつつ、気持ちよく退職するためのポイントを押さえておきましょう。
- 感謝の気持ちを伝える – 上司や同僚に「お世話になりました」と一言伝えるだけでも印象がよくなる
- 引き継ぎを丁寧に行う – 退職後も職場が円滑に回るよう、細かい部分まで引き継ぐ
- 退職理由は前向きに伝える – 「スキルアップのため」「新しい挑戦をしたい」など、ポジティブな理由を述べる
- 最後まで責任を持つ – 退職日まで仕事をしっかりやり遂げる
- 職場の悪口を言わない – 退職後もどこでつながるかわからないため、ネガティブな発言は控える
円満退職を心がけることで、次の職場でも気持ちよくスタートを切ることができます。
退職後の手続きと注意点
退職後は、社会保険や税金などの手続きを忘れずに行うことが重要です。
手続きを怠ると、思わぬトラブルに巻き込まれることもあるため、しっかりと確認しておきましょう。
- 健康保険の手続き – 退職後、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入るかを決める
- 年金の手続き – 厚生年金から国民年金に切り替える必要がある
- 失業保険の申請 – 退職後にハローワークで手続きを行い、給付を受けられるか確認する
- 住民税の支払い – 退職後も住民税の支払い義務があるため、支払い方法を確認する
- 転職活動の準備 – 次の仕事に向けて、履歴書や職務経歴書を作成しておく
退職後の手続きを適切に行うことで、新しい生活をスムーズにスタートできます。
転職活動の具体的な進め方
退職後にスムーズに転職できるよう、計画的に転職活動を進めることが大切です。
次の職場を見つけるためには、以下のステップを踏みましょう。
- 自己分析を行う – 自分の強みや適性を整理し、どのような仕事に向いているかを考える
- 求人をリサーチする – 転職サイトや求人情報を活用し、自分に合った職場を探す
- 履歴書と職務経歴書を作成する – 採用担当者に魅力的に映るように、しっかりと作り込む
- 面接対策をする – よく聞かれる質問を想定し、スムーズに回答できるよう練習する
- 転職エージェントを活用する – プロのサポートを受けながら、効率よく転職活動を進める
転職活動は準備が重要です。
しっかり計画を立てて、新しい職場を見つけましょう。
新しいキャリアで成功するための準備
新しい職場で成功するためには、事前の準備が大切です。
転職後にスムーズに仕事を始めるために、以下の点を意識しましょう。
- 新しい職場の文化を理解する – 会社の方針やルールを早めに把握し、適応する
- 必要なスキルを学ぶ – 事前に仕事に必要な知識や技術を学んでおく
- 人間関係を築く – 新しい同僚と積極的にコミュニケーションをとり、良好な関係を作る
- 柔軟な姿勢を持つ – 転職先のやり方に慣れるために、素直に学ぶ姿勢を持つ
- 成長を意識する – 長期的な視点でキャリアアップを考え、学び続ける
転職後に成功するためには、前向きな姿勢としっかりした準備が欠かせません。
新しい環境でのスタートを、最高のものにしましょう。
まとめ

新卒保健師として働き始めたものの、「辞めたい」と感じることは決して珍しいことではありません。
仕事の悩みを整理し、次のキャリアの選択肢をしっかり考えることが大切です。
この記事のポイントを簡単にまとめました。
- 辞めたい理由を整理する – 仕事のストレス、人間関係、給与、将来性など、原因を明確にする
- 退職を決断する前に選択肢を考える – 転職、休職、異動など、退職以外の解決策も検討する
- 保健師資格を活かせる仕事を探す – 産業保健師、医療職、一般企業など、幅広いキャリアがある
- 円満退職を心がける – 退職の手順を守り、感謝の気持ちを伝える
- 転職活動の準備をする – 自己分析、スキルアップ、履歴書作成、面接対策を行う
大切なのは、自分にとって最善の選択をすることです。
焦らずじっくり考え、新しいキャリアへ前向きに進んでいきましょう。







