行政保健師の仕事は住民の健康を支える大切な役割ですが、日々の業務の中で「このまま続けていけるのか」と悩むこともありますよね。
職場の人間関係、業務の負担、ワークライフバランスの崩れなど、退職を考える理由は人それぞれです。
今回は、行政保健師が退職を決意する理由と転職先の選び方について詳しく解説します。
どんな選択肢があるのかを知ることで、より良いキャリアを築くためのヒントが得られます。
この記事を読むことで、退職前に考えるべきポイントや、円満退職の方法、次のキャリアの選び方が分かります。
自分に合った働き方を見つけるために、ぜひ最後まで参考にしてください。
行政保健師が退職を決意する主な理由

職場環境のストレスと人間関係
職場環境のストレスや人間関係の悩みは、行政保健師が退職を考える大きな要因の一つです。
特に、役所や自治体の組織は縦割りの文化が強く、人間関係の悩みが生じやすい特徴があります。
以下のような理由でストレスを感じることが多いです。
- 上司や同僚との関係が難しい…行政の仕事では、上司や先輩の指示に従う場面が多く、意見が通りにくいことがあります。
- チームワークが求められる…職場では他部署との連携が必要ですが、連携がスムーズにいかずストレスになることがあります。
- クレーム対応が負担…住民対応をする機会が多く、中には厳しい意見を言われることもあり、精神的な負担が大きくなります。
- 仕事の分担が偏る…一部の人に業務が集中し、不公平感が生まれることで不満が募ります。
- ハラスメントの問題…職場によってはパワハラやセクハラの問題があり、相談しても改善されないこともあります。
このような状況が続くと、仕事への意欲が低下し、最終的に退職を考える人が増えてしまいます。
業務の負担とワークライフバランスの崩れ
行政保健師の仕事は多岐にわたり、業務量が多くなりがちです。
特に、感染症対応や地域の健康促進業務が増えると、仕事の負担が大きくなり、プライベートの時間が削られることがあります。
主な原因として、以下の点が挙げられます。
- 残業が多い…住民の健康相談や緊急対応が発生すると、勤務時間外でも対応しなければならないことがあります。
- 休日出勤が発生する…地域イベントや健康教室の運営などで、土日出勤が求められることもあります。
- 業務範囲が広すぎる…健康指導、調査、研修の企画など、多岐にわたる業務をこなさなければならず、負担が増えます。
- 休暇が取りにくい…人手不足のため、まとまった休みが取りにくく、リフレッシュする機会が減ります。
- 緊急対応が頻繁にある…感染症の流行時には急な対応が求められ、精神的なプレッシャーも大きくなります。
このように、ワークライフバランスが崩れると、心身ともに疲れ果ててしまい、退職を考えるようになります。
キャリアアップやスキルアップの限界
行政保健師として働いていると、自分の成長やスキルアップの機会が限られると感じることがあります。
行政の仕事は安定している一方で、以下のような理由からキャリアの選択肢が狭まることがあります。
- 昇進の機会が少ない…ポストが限られており、上が詰まっているため、キャリアアップが難しいことがあります。
- 専門性を深める機会が少ない…幅広い業務をこなすことが求められるため、一つの分野を極めることが難しいです。
- 新しいチャレンジがしにくい…行政の仕事はルールや制度に縛られるため、自由に新しい取り組みを進めることが難しいです。
- 民間の医療や福祉の現場と比べて変化が少ない…民間では新しい技術や手法が取り入れられることが多いですが、行政は変化が遅い傾向があります。
- 転職市場での価値が見えにくい…行政の仕事は特殊なため、他の業界に転職する際にスキルのアピールが難しいと感じることがあります。
このような理由から、もっと成長できる環境を求めて転職を考える行政保健師も多いのです。
収入や待遇への不満
行政保健師の給与や待遇に不満を持つ人も少なくありません。
公務員は安定した職業ですが、収入面での悩みがあることも事実です。
特に以下のような点が問題になります。
- 昇給のペースが遅い…公務員の給与は年功序列のため、若いうちは収入が少なく感じることがあります。
- 賞与の増減がある…自治体の財政状況によっては、ボーナスが減ることもあります。
- 手当が少ない…民間企業と比べて、残業代や資格手当が少ないことがあります。
- 副業が禁止されている…公務員は副業が制限されているため、収入を増やしたくても手段が限られます。
- 民間企業と比べて給与が低い…産業保健師や病院勤務の保健師と比べると、給与が見劣りすることがあります。
給与や待遇面の不満が大きくなると、より良い条件を求めて転職を考えるようになります。
家庭やライフスタイルの変化
結婚や出産、家族の介護など、ライフスタイルの変化が行政保健師の退職理由になることもあります。
仕事と家庭の両立が難しくなると、転職を検討する人が増えます。
- 育児と仕事の両立が難しい…夜間対応や休日出勤があるため、小さな子どもがいる家庭では負担が大きいです。
- 配偶者の転勤…結婚後、パートナーの転勤に伴い退職を選ぶ人もいます。
- 介護の必要性…親の介護が必要になり、柔軟な働き方ができる職場を探すケースがあります。
- ライフスタイルの変化…地方移住やフリーランスへの転向など、新しい働き方を求める人もいます。
このように、ライフスタイルの変化によって行政保健師の仕事を続けることが難しくなる場合もあります。
行政保健師の退職を決める前に考えるべきこと

退職後の生活設計とキャリアプラン
退職を考えたときに、まず考えるべきなのは「退職後の生活をどのようにするか」ということです。
特に、転職するのか、しばらく休むのか、全く違う業界に挑戦するのかなど、しっかり計画を立てることが重要です。
退職後の生活をスムーズに進めるために、次のポイントを考えましょう。
- 今後の働き方を決める…転職するのか、フリーランスになるのか、家庭に専念するのかを考える。
- 必要なスキルを洗い出す…転職を考えている場合、次の職場で求められるスキルを確認し、事前に準備する。
- 収入源の確保…退職後すぐに収入がないと不安が大きいため、貯金や退職金の使い方を考える。
- ライフスタイルに合わせた仕事選び…家庭や趣味とのバランスを考え、無理のない働き方を選ぶ。
- 長期的なキャリアプランを考える…今後の10年、20年のキャリアをどう築いていくかをイメージする。
退職後の生活をしっかり設計しておけば、後悔のない決断ができます。
退職時の手続きと必要な準備
退職を決めたら、円滑に手続きを進めるための準備が必要です。
行政保健師は公務員であるため、民間企業とは異なる手続きが求められることもあります。
具体的には、次のような準備を進めましょう。
- 退職願・退職届の準備…退職願を提出する前に、上司に相談して適切な時期を決める。
- 退職までのスケジュールを調整…引継ぎ業務を考慮し、退職日までのスケジュールを明確にする。
- 必要書類の確認…退職後の年金や健康保険の手続きに必要な書類を準備する。
- 失業保険の確認…ハローワークで失業手当の受給資格を調べ、必要ならば手続きを行う。
- 職場への感謝を伝える…円満退職のために、最後まで誠実に対応し、感謝の気持ちを伝える。
適切な準備をしておくことで、退職後に慌てることなくスムーズに新しい生活をスタートできます。
退職理由を明確にして今後の方向性を決める
退職を考えたとき、まず「なぜ辞めたいのか」を明確にすることが重要です。
単に不満を抱えて辞めるのではなく、前向きな理由を見つけることで、次のステップに進みやすくなります。
- 現在の仕事の何に不満を感じているか…業務内容、人間関係、待遇、ワークライフバランスなどを具体的に整理する。
- 退職しなければ解決できない問題か…部署異動や働き方の見直しで解決できるかどうかを検討する。
- 次にどんな仕事をしたいのか…どのような業界・職種で働きたいかを明確にする。
- 新しい仕事で何を重視するか…給与、働き方、やりがい、人間関係などの優先順位を決める。
- 退職後に後悔しないための準備…転職活動を先に始めるなど、リスクを減らす工夫をする。
退職理由をしっかり整理することで、次のキャリア選択をより良いものにできます。
転職活動のスケジュールと準備
退職を決めたら、次に重要なのは転職活動のスケジュールと準備です。
特に、行政保健師から他の仕事に転職する場合は、スムーズに進めるための計画が必要になります。
- 転職活動を始める時期を決める…退職前から始めるのか、退職後に本格的に進めるのかを考える。
- 自己分析を行う…自分の強みや経験を整理し、どの業界・職種に向いているかを確認する。
- 求人情報を集める…転職サイトやエージェントを活用し、条件に合う仕事を探す。
- 履歴書・職務経歴書を準備する…行政保健師としての経験を活かせるように書類を作成する。
- 面接対策を行う…公務員からの転職に関する質問に答えられるように準備する。
しっかりと準備をしておけば、スムーズに転職活動を進めることができます。
公務員退職のメリット・デメリット
公務員を辞めることには、メリットとデメリットの両方があります。
退職を決める前に、しっかりと比較検討することが大切です。
公務員を退職するメリット
- 自由な働き方ができる…公務員のルールに縛られず、自分のやりたい仕事を選べる。
- スキルアップの機会が増える…民間企業では専門性を磨く機会が多く、新しい知識を身につけやすい。
- 収入アップの可能性がある…実力次第で昇給が見込めるため、年収が増える可能性がある。
- キャリアの幅が広がる…民間企業やフリーランスなど、さまざまな道を選べる。
公務員を退職するデメリット
- 安定した収入がなくなる…民間企業では業績によって給与が変動するため、不安定になることもある。
- 福利厚生が手薄になる…公務員は手厚い福利厚生があるが、民間ではそれが少ない場合がある。
- 転職活動が難しくなることがある…公務員経験が民間でどのように評価されるかは職種によって異なる。
公務員を辞めることには良い面と悪い面があるため、慎重に判断することが大切です。
行政保健師の転職先の選び方とおすすめの職種

民間企業の産業保健師として働く
行政保健師からの転職先として、民間企業の産業保健師は非常に人気があります。
産業保健師は、企業で働く従業員の健康管理を担当し、健康診断のフォローやメンタルヘルスケアなどを行います。
行政保健師としての経験を活かせる場面も多いため、スムーズに転職できる可能性が高いです。
産業保健師の主な業務
- 健康診断の実施・結果管理…従業員の健康診断のスケジュール管理や結果の確認を行う。
- 職場のメンタルヘルス対策…ストレスチェックの実施や、メンタル不調者の相談対応を行う。
- 職場環境の改善…労働環境の衛生管理や、安全な職場づくりのための提案をする。
- 休職・復職支援…病気や精神的な不調で休職する従業員の復職支援を行う。
- 健康教育の実施…社員向けの健康セミナーや運動プログラムを企画する。
産業保健師は企業に雇われるため、勤務時間が安定しており、給与も行政保健師より高い傾向があります。
特に大企業では待遇が良いことが多く、転職を成功させるとワークライフバランスが向上する可能性があります。
医療機関や福祉施設での保健指導
行政保健師からの転職先として、病院やクリニック、福祉施設での保健指導業務も選択肢の一つです。
医療機関では、患者や利用者への健康指導が主な業務となり、行政で培った保健指導のスキルを活かせます。
医療機関・福祉施設での主な仕事
- 生活習慣病予防指導…糖尿病や高血圧などの予防策を指導する。
- 高齢者の健康管理…介護施設などで入居者の健康状態をチェックし、適切なアドバイスを行う。
- リハビリ支援…病気やケガからの回復をサポートし、生活改善を促す。
- 患者や家族への健康教育…病気の管理方法や予防策についてわかりやすく説明する。
- 地域住民向けの健康相談…地域の人々に向けて健康講座を開く。
医療機関で働く場合、看護師資格を持っているとより多くの職場で活躍できる可能性が高まります。
専門性をさらに高めたい人におすすめの転職先です。
教育機関での健康管理業務
学校や大学などの教育機関で働くのも、行政保健師からの転職先として考えられます。
特に、養護教諭や大学の保健室勤務など、子どもや学生の健康管理に関わる仕事が多いです。
教育機関での主な業務
- 生徒・学生の健康管理…健康診断や日々の体調管理を行う。
- 健康相談…学校内での怪我や病気の対応、メンタルヘルス相談を受ける。
- 感染症対策…学校内でのインフルエンザやノロウイルスの予防対策を立てる。
- 保護者や教員との連携…生徒の健康状態を保護者や担任教師と共有する。
- 健康教育の実施…食生活や睡眠、ストレス管理について授業を行う。
学校での勤務は子どもが好きな人に向いている職場です。
また、長期休暇があるため、家庭と仕事の両立がしやすい点もメリットの一つです。
フリーランスや独立して活動する方法
最近では、行政保健師の経験を活かしてフリーランスとして独立する人も増えています。
企業や自治体と契約し、健康セミナーの講師やコンサルタントとして働く道もあります。
フリーランスの主な仕事
- 健康セミナーの講師…企業や自治体向けに、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策のセミナーを行う。
- オンライン健康相談…個人向けに健康相談を実施し、生活改善のアドバイスをする。
- ヘルスライター…健康や医療に関する記事を執筆し、メディアに提供する。
- 企業の健康管理アドバイザー…企業の従業員向け健康管理プログラムの設計や指導を行う。
- YouTubeやSNSでの発信…健康に関する情報を発信し、影響力を高める。
フリーランスになると自分のペースで働ける反面、収入が不安定になるリスクもあります。
そのため、独立を目指す場合は、事前に十分な準備が必要です。
行政以外の公的機関での再就職
行政保健師を辞めた後でも、別の公的機関で働く道があります。
例えば、国や都道府県の保健所、社会福祉法人、NPOなどが転職先の候補になります。
公的機関での主な仕事
- 保健所の職員…感染症対策や地域住民への健康指導を行う。
- NPOや社会福祉法人…社会的に支援が必要な人々の健康管理をサポートする。
- 厚生労働省や自治体の専門職…行政の視点から医療や福祉の制度を企画・運営する。
行政保健師としての経験を活かしつつ、新しい環境で働けるため、安定性を求める人に向いている転職先です。
行政保健師が円満に退職するための注意点

退職願・退職届の書き方と提出タイミング
退職を決意したら、退職願や退職届を適切なタイミングで提出することが重要です。
行政保健師は公務員であるため、一般企業とは異なるルールがある場合もあります。
スムーズな退職のために、次の点を意識しましょう。
退職願と退職届の違い
- 退職願…「退職したい」という意志を伝える書類。
- 退職届…「退職することが決定した」際に提出する正式な書類。
退職の適切なタイミング
- 3~6か月前…上司に相談し、退職の意向を伝える。
- 1~2か月前…退職願を提出し、業務の引継ぎを開始する。
- 2週間前~1か月前…退職届を提出し、正式に退職日を決定する。
適切な時期に手続きを進めることで、職場との関係を良好に保ちながら退職できます。
引継ぎ業務の進め方と注意点
退職する際には、業務の引継ぎをしっかり行うことが大切です。
後任者がスムーズに業務を進められるよう、次の点を意識して引継ぎを進めましょう。
引継ぎのポイント
- 業務内容を整理する…自分が担当している業務をリストアップし、優先順位をつける。
- マニュアルを作成する…後任者が困らないよう、業務の流れを記録しておく。
- 関係者への引継ぎを行う…同僚や関係部署に必要な情報を共有する。
- トラブル時の対応方法を伝える…過去の事例や注意点を説明し、スムーズな業務遂行をサポートする。
- 引継ぎの進捗を管理する…計画的に進め、退職直前に慌てないようにする。
適切な引継ぎを行うことで、職場に迷惑をかけずに円満退職ができます。
円満退職のための上司や同僚への対応
退職を決めたら、上司や同僚にどのように伝えるかも重要なポイントになります。
職場の雰囲気を悪くせずに退職するためには、以下の点を心がけましょう。
上司への対応
- 早めに相談する…退職の意向を早めに伝え、スムーズな調整を行う。
- 感謝の気持ちを伝える…これまでの指導やサポートに対してお礼を述べる。
- 退職理由はポジティブに…ネガティブな言い方を避け、前向きな理由を伝える。
同僚への対応
- 正式に決まってから伝える…噂が広がらないよう、正式に決定してから報告する。
- 業務の引継ぎをしっかり行う…迷惑をかけないよう、しっかり引継ぎをする。
- 感謝を忘れない…一緒に働いたことへの感謝を伝える。
円満退職を意識することで、退職後も良好な関係を維持することができます。
退職後の人間関係を良好に保つコツ
退職後も、元同僚や上司との関係を良好に保つことは大切です。
特に、同じ業界に転職する場合や、将来的に仕事で関わる可能性がある場合は、良い関係を維持しておくことでメリットが生まれます。
退職後も良好な関係を続けるためのポイント
- 退職の挨拶をしっかり行う…最後の印象を良くするために、丁寧に挨拶する。
- 退職後も適度に連絡を取る…年賀状やSNSなどで近況報告を行う。
- 悪い噂を流さない…退職後に元職場の悪口を言わないようにする。
- 仕事の相談があれば快く受ける…必要に応じて、前職の同僚や上司の相談にのる。
良好な関係を続けておくことで、転職後に困ったときの助けにもなります。
退職後の公務員としての守秘義務
行政保健師として働いた経験がある場合、退職後も守秘義務があることを忘れてはいけません。
公務員は職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはいけないという規則があり、これを破ると法律違反になる可能性があります。
公務員の守秘義務のポイント
- 住民の個人情報を漏らさない…業務で知った個人の健康情報を外部に話さない。
- 行政の内部情報を公開しない…役所の運営方法や政策の詳細を勝手に話さない。
- 退職後も義務が続く…退職したからといって守秘義務がなくなるわけではない。
守秘義務を守ることで、社会的信用を失わず、安心して新しい仕事に取り組むことができます。
退職時に確認すべき公務員の福利厚生
行政保健師が退職する際には、公務員ならではの福利厚生の確認も重要です。
特に、退職金や年金、健康保険などは事前にしっかり把握しておきましょう。
退職前に確認するべきポイント
- 退職金の金額…勤務年数によって変わるため、事前に確認しておく。
- 健康保険の切り替え…退職後は国民健康保険に加入する必要があるかを調べる。
- 厚生年金・共済年金…退職後の年金の受給資格や手続きを確認する。
公務員ならではの制度を活用することで、退職後の生活をスムーズに進めることができます。
まとめ
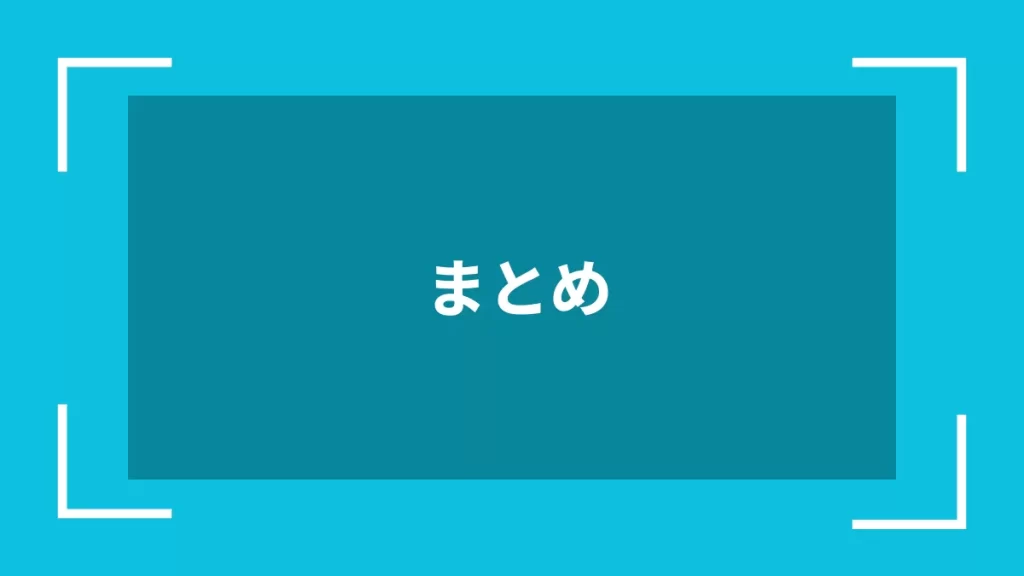
行政保健師の退職を考えるとき、理由や今後の選択肢を明確にすることが大切です。
転職を成功させるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 退職を決意する理由を整理する…職場環境、人間関係、業務量、収入、キャリアアップなどを明確にする。
- 退職前に必要な準備を進める…退職願・退職届の提出、引継ぎ、必要な手続きを計画的に行う。
- 転職先の選択肢を広げる…産業保健師、医療機関、教育機関、フリーランス、公的機関などを検討する。
- 退職後の生活設計を考える…収入や働き方を見直し、キャリアプランをしっかり立てる。
- 円満退職を心がける…職場の人間関係を大切にし、退職後も良好な関係を維持する。
退職は新しい人生のスタートです。
後悔しないように準備をしっかり行い、自分に合った道を選びましょう。







