公務員保健師として働いていると、「理想と現実のギャップが大きい」と感じたり、「この仕事を続けていていいのか不安になる」ことがありますよね。
人間関係や給与、働き方に悩み、転職を考える方も少なくありません。
今回は、公務員保健師が辞める理由と転職のポイントについて詳しく解説します。
退職を考える際に気をつけるべきことや、転職先の選び方、円満に退職する方法までしっかりお伝えします。
転職を成功させるためのポイントが分かれば、自分に合った新しい働き方を見つけることができます。
後悔のない選択をするために、ぜひ最後まで参考にしてください。
公務員保健師が辞める主な理由
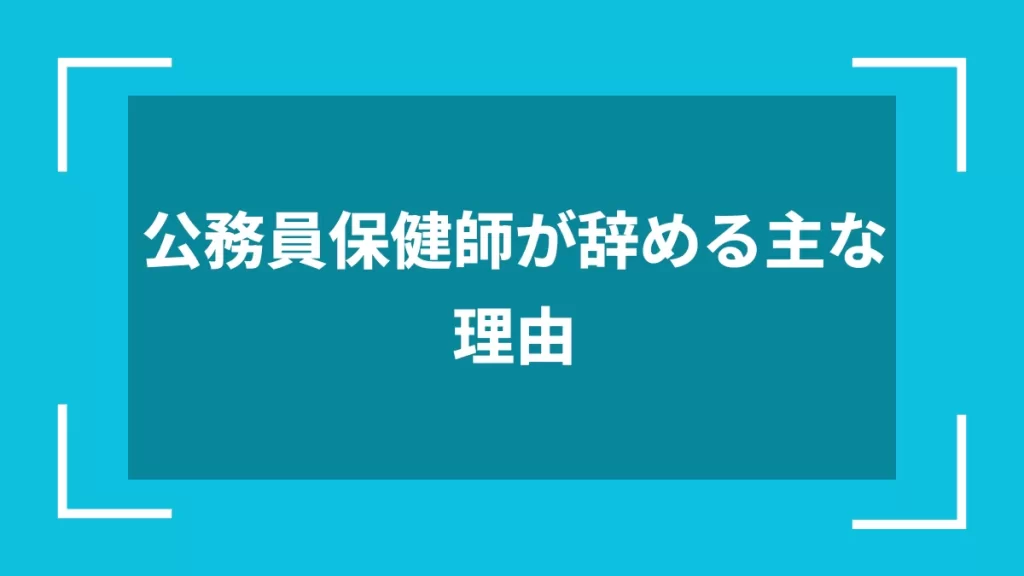
仕事内容と理想のギャップ
公務員保健師として働く中で、実際の業務が理想と大きく異なると感じる人は少なくありません。
大学や専門学校で学んだ内容と現場の実態にズレがあると、やりがいを感じにくくなることがあります。
特に以下のような点がギャップとして挙げられます。
- 住民対応が中心 – 保健指導や健康相談の業務が多く、臨床での経験を活かしにくい
- デスクワークが多い – 統計作成や報告書の作成が多く、現場での活動が想像より少ない
- 即効性のある支援が難しい – 住民の健康改善には時間がかかり、すぐに成果を実感しづらい
- 法律や規則に縛られる – 施策や制度に基づいた業務が多く、柔軟な対応がしにくい
- 専門職としての裁量が少ない – 自分の判断よりも、行政の方針に従うことが求められる
このようなギャップを感じることで、仕事に対するモチベーションが低下し、転職を考える保健師もいます。
職場の人間関係の悩み
公務員保健師の職場では、人間関係が大きなストレス要因になることがあります。
特に以下のような点が問題になりやすいです。
- 上下関係が厳しい – 上司や先輩との関係に気を使いすぎてしまう
- チームワークが重視される – 個人の意見よりも、組織全体の意向が優先される
- 異動が多い – 異動ごとに新しい人間関係を築く必要がある
- 医療職以外の職員との考え方の違い – 他職種との連携に苦労することがある
- 公務員特有の文化 – 民間企業と異なり、柔軟な働き方が難しい
人間関係のストレスが続くと、仕事への意欲が低下し、退職を考える原因になります。
給与・待遇への不満
公務員保健師の給与や待遇に不満を感じる人も多く、転職を考えるきっかけとなることがあります。
具体的な不満点として、次のようなものがあります。
- 給与が民間と比べて低い – 病院や企業の保健師と比べると、給与水準が低め
- 昇給スピードが遅い – 年功序列の影響で、給与がなかなか上がらない
- 残業代がつかない場合がある – みなし残業や業務外の対応が多い
- ボーナスが安定しているが高額ではない – 民間企業の成果給に比べると、収入増が見込めない
- 資格やスキルに対する手当が少ない – 専門職としての評価が給与に反映されにくい
こうした不満が蓄積すると、より良い待遇を求めて転職を考える人が増えます。
ワークライフバランスの問題
公務員保健師は定時退社できるイメージがありますが、実際にはワークライフバランスに悩む人もいます。
以下のような要因が関係しています。
- 住民対応が長引く – 相談業務が終わらず、残業になることがある
- 休日出勤がある – 健康イベントや災害対応で休日勤務が必要になることも
- 家庭との両立が難しい – 育児や介護と両立しにくい場合がある
- 有給休暇が取りづらい – 人員が少なく、長期休暇が取りにくい
- 精神的な疲労が蓄積する – 住民の健康相談やケース対応でメンタル負担が大きい
このような状況が続くと、プライベートとの両立が難しくなり、退職を決意する人が増えます。
キャリアの将来性に対する不安
公務員保健師として働く中で、「このままでいいのか」と将来に不安を感じる人も少なくありません。
特に次のような点が問題になります。
- キャリアアップの道が限られている – 管理職や専門職への昇進が難しい
- スキルが偏る – 行政業務に特化しすぎて、民間で活かしにくい
- 転職の選択肢が狭まる – 公務員経験が他業種で評価されにくい
- 自分の専門性が活かせない – 一般事務のような業務が多く、専門知識が活かせない
- 定年まで働き続けることへの不安 – この仕事を一生続けるイメージが持てない
将来のキャリアを見据えたときに、より自分に合った働き方を求めて転職を考える保健師が多いです。
公務員保健師を辞める前に考えるべきこと
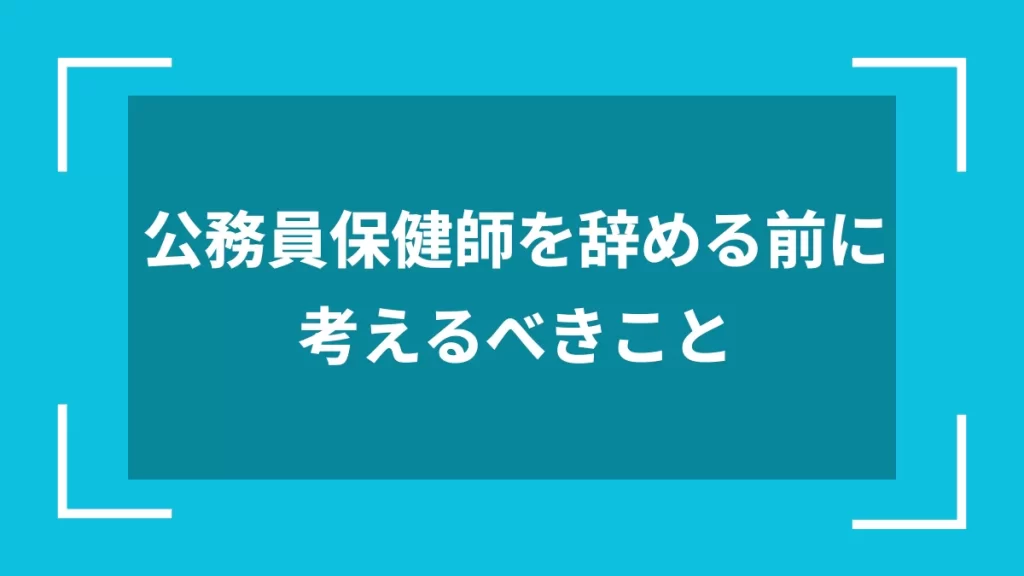
転職の目的を明確にする
公務員保健師を辞める前に、まず転職の目的を明確にすることが大切です。
目的が不明確なまま退職すると、次の仕事でも同じ悩みを抱える可能性があります。
転職を成功させるために、以下のような点を整理しましょう。
- 何が一番の不満なのか – 仕事内容、人間関係、給与、キャリアのどこに問題を感じるのか
- どんな働き方をしたいのか – 民間企業や病院、フリーランスなどの選択肢を考える
- どんな職場環境が理想か – チームワーク重視か、個人で働く環境が良いか
- 専門スキルをどう活かすか – 保健師の知識を生かせる仕事なのか、新しい分野に挑戦するのか
- 収入面の希望 – 現状の給与に不満があるのか、安定よりもやりがいを求めるのか
これらの点を明確にすることで、転職後の後悔を防ぐことができます。
辞めた後のリスクと対策
公務員保健師を辞めた後には、さまざまなリスクが伴います。
転職を決意する前に、どんなリスクがあるのかを知り、事前に対策を考えておくことが大切です。
- 収入が不安定になる – 退職後すぐに新しい仕事が決まらない可能性がある
- 転職先が合わない場合がある – 実際に働いてみたら理想と違うこともある
- 人間関係の悩みはどこにでもある – 転職しても職場の人間関係で悩むことはありえる
- スキルが評価されない可能性がある – 公務員経験が民間企業で直接活かせないことがある
- 福利厚生が減ることがある – 公務員ならではの安定した待遇がなくなることもある
これらのリスクを避けるためには、事前に転職市場の情報を集め、しっかりと準備することが重要です。
転職市場における保健師の需要
公務員保健師を辞めた後に、どのような仕事に転職できるのか気になる人も多いでしょう。
保健師の資格を活かせる仕事は意外と多く、需要もあります。
主な転職先として、次のようなものが考えられます。
- 産業保健師 – 企業で従業員の健康管理を担当し、給与水準も比較的高い
- 病院やクリニック – 医療現場で保健指導や健康相談を行う
- 民間の健康関連企業 – 健康食品メーカーやフィットネス業界で働く
- 教育機関の保健師 – 学校保健師として、児童や学生の健康管理を担当する
- フリーランスの健康アドバイザー – 独立してオンラインで健康相談を行う
転職市場における保健師の需要は高く、特に産業保健師や病院勤務の求人が多く見られます。
退職時の手続きと注意点
公務員保健師を辞める際には、いくつかの手続きが必要になります。
スムーズに退職するために、事前に準備を進めておきましょう。
- 退職届の提出 – 所属機関のルールに従い、適切なタイミングで提出する
- 有給休暇の消化 – できるだけ有給を使い切るように調整する
- 引き継ぎ資料の作成 – 後任者が困らないよう、業務の流れをまとめておく
- 退職金の確認 – 退職時に支給される退職金の計算を確認する
- 転職先の決定 – 退職前に次の仕事を決めておくと安心
円満退職のためには、最後まで誠実に対応することが大切です。
転職活動と在職中の両立方法
退職を考えている人の中には、在職中に転職活動を進めるべきか悩む人も多いでしょう。
仕事を続けながら転職活動をするのは大変ですが、リスクを減らすためにはおすすめの方法です。
以下のポイントを意識すると、スムーズに転職活動を進めることができます。
- 転職サイトやエージェントを活用する – 効率的に求人情報を集める
- 面接は有給を使って調整 – 平日に面接を受ける際は計画的に休みを取る
- 退職のタイミングを見極める – 転職先が決まってから辞めるのが理想
- 家族や身近な人に相談する – 一人で悩まず、周囲の意見を聞く
- 仕事に影響を与えないようにする – 転職活動がバレないよう注意する
仕事を続けながら転職活動を進めることで、収入の不安を抱えずに新しい職場を探すことができます。
公務員保健師からの転職先の選び方
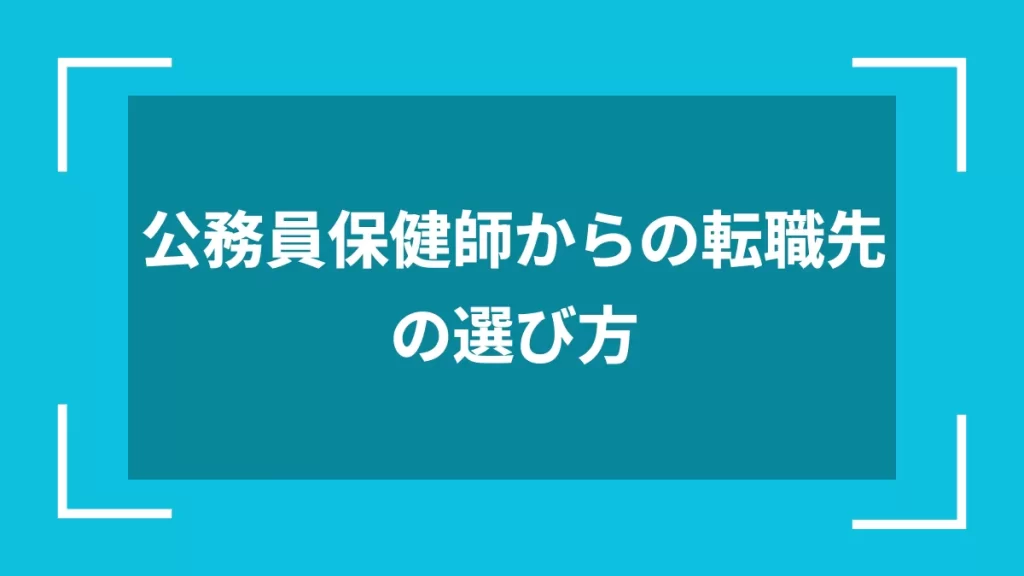
病院・クリニックでの保健師業務
公務員保健師から病院やクリニックへ転職する人は多く、医療現場で直接患者と関わりたい人に向いています。
公務員時代の経験を活かしながら、より医療的なアプローチができるのが特徴です。
病院やクリニックでの保健師業務には、以下のような魅力があります。
- 患者との距離が近い – 健康相談や予防医療のアドバイスを直接提供できる
- 医療職としてのスキルを活かせる – 臨床知識を使う機会が増える
- 医師や看護師と連携しやすい – 医療チームの一員として働くことができる
- キャリアアップが可能 – 経験を積めば、管理職や専門職に進める
- 働き方の選択肢が広がる – 日勤のみの職場や非常勤勤務なども選べる
病院やクリニックでの保健師業務は、より医療に密接した仕事を求める人に最適な選択肢です。
企業の産業保健師への転職
企業で働く産業保健師は、従業員の健康管理やメンタルヘルスのサポートを担当する重要な仕事です。
安定した環境で働きながら、専門知識を活かせる点が魅力です。
産業保健師として働くメリットには、以下のようなものがあります。
- 給与が高め – 公務員保健師よりも給与水準が高い傾向がある
- 働きやすい環境 – 残業が少なく、土日休みの職場が多い
- 専門性を発揮できる – ストレスチェックや健康管理業務を担当できる
- 福利厚生が充実 – 大手企業ほど手厚い待遇がある
- キャリアの選択肢が広がる – 企業間の転職がしやすく、経験を活かせる
産業保健師は、ワークライフバランスを重視しながら働きたい人におすすめの転職先です。
行政以外の公的機関での活躍
公務員保健師を辞めても、他の公的機関で働く道があります。
例えば、社会福祉法人や非営利団体(NPO)、研究機関などで保健師の知識を活かすことができます。
公的機関での保健師業務には、以下のような選択肢があります。
- 地域包括支援センター – 高齢者の健康相談や支援を行う
- 保育園・学校 – 子どもたちの健康管理や保健指導を担当する
- 大学・研究機関 – 健康に関する調査や研究に携わる
- 国際機関・NPO – 海外での保健活動や支援業務を行う
- 医療系財団法人 – 公衆衛生や健康政策の立案に関与する
公的機関での仕事は、社会貢献度が高く、やりがいを求める人に向いています。
看護師・医療職へのキャリアチェンジ
保健師資格を持っている人の中には、看護師や他の医療職にキャリアチェンジする人もいます。
特に、医療現場での経験を積みたい人や、収入アップを目指す人におすすめの道です。
具体的な選択肢として、以下のようなものがあります。
- 看護師への転職 – 看護師免許があれば、病院やクリニックで勤務できる
- 訪問看護 – 高齢者や在宅医療のニーズが高まり、需要がある
- 助産師 – 女性の健康支援に特化した仕事をしたい人に向いている
- 理学療法士・作業療法士 – リハビリ分野で活躍できる資格
- 医療ソーシャルワーカー – 患者や家族の相談支援を行う
看護師や医療職への転職は、より専門的な知識を活かしたい人に適しています。
保健師資格を活かせる民間企業の仕事
保健師資格を活かせる仕事は、民間企業にも多くあります。
医療関連の企業や健康サービスを提供する企業で活躍する道もあります。
主な職種として、以下のような選択肢があります。
- 健康コンサルタント – 企業や個人向けに健康管理のアドバイスを行う
- 健康食品・製薬会社 – 商品開発やマーケティングに関わる
- フィットネス業界 – 健康促進のプログラムを提供する
- オンラインヘルスケアサービス – 健康相談やカウンセリングをオンラインで実施
- 医療機器メーカー – 製品の安全性評価や販売支援に関与
民間企業での仕事は、専門知識を活かしながら新しい分野に挑戦したい人に向いています。
フリーランスや独立の可能性
最近では、フリーランスの保健師として独立する人も増えています。
特定の企業や団体に所属せず、自分のスキルを活かして自由に働けるのが特徴です。
フリーランス保健師の働き方には、以下のようなものがあります。
- オンライン健康相談 – SNSやブログを活用して健康アドバイスを提供
- 講師・セミナー業 – 健康や保健に関する講座を開催
- ライター・監修 – 健康や医療関連の記事を執筆
- 企業向け健康指導 – 産業保健分野でのアドバイザーとして活動
- 行政と連携した地域活動 – 地域の健康支援事業を立ち上げる
フリーランスとして働くことで、自分の得意分野を活かしながら自由な働き方を実現できます。
公務員保健師が円満に退職する方法
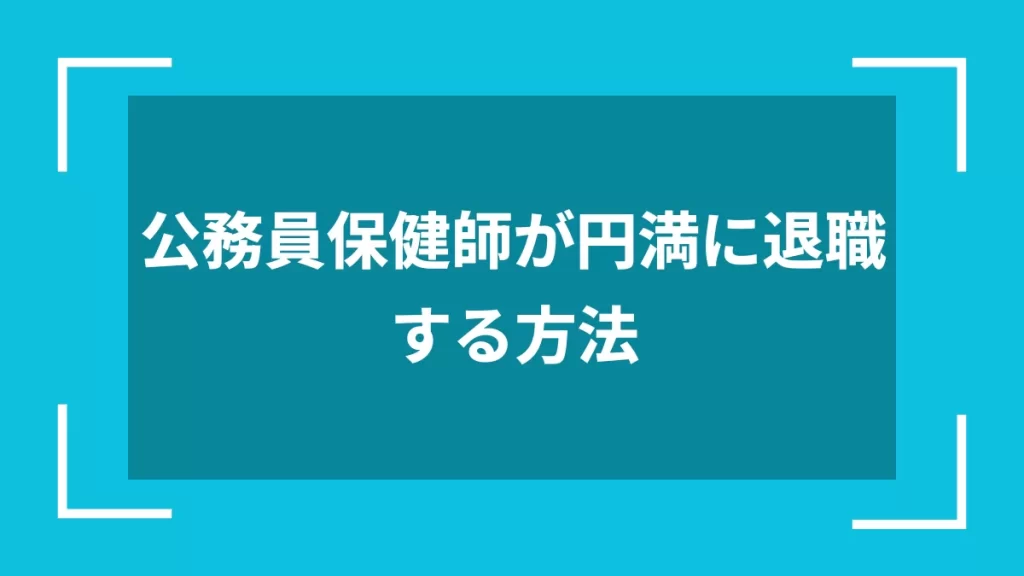
上司や同僚への伝え方
退職を決めたら、まず上司や同僚にどのように伝えるかが重要です。
円満に退職するためには、適切なタイミングと伝え方を考えましょう。
以下のポイントを意識すると、スムーズに話を進められます。
- 報告は直属の上司から – 先に同僚に話すとトラブルの原因になる
- 退職の意思は早めに伝える – 退職希望日の2~3ヶ月前が目安
- 感謝の気持ちを伝える – 不満があっても前向きな理由を伝える
- 退職理由は簡潔に – 「新しい挑戦をしたい」「別の分野で経験を積みたい」と伝える
- 円満な引継ぎを約束する – できる限り協力的な姿勢を示す
上司や同僚に誠意を持って伝えることで、円満な退職が可能になります。
引継ぎ業務の進め方
公務員保健師として働いた業務は、次の担当者にしっかり引き継ぐ必要があります。
引継ぎがスムーズに進めば、退職後の職場環境にも良い影響を与えます。
以下のポイントを意識して準備しましょう。
- 業務リストを作成する – 担当していた仕事を整理し、一覧にする
- 手順書やマニュアルを作成 – 次の担当者が困らないように、業務の流れをまとめる
- 関係者へ業務の進行状況を共有 – 進行中の業務や今後の予定を伝える
- 後任者と面談の機会を持つ – 直接話すことで、不明点を減らせる
- 最終出勤日まで誠実に対応 – 途中で手を抜かず、最後まで責任を持つ
しっかりと引継ぎを行うことで、退職後も良い印象を持たれるでしょう。
退職時に必要な書類と手続き
退職する際には、いくつかの書類や手続きを進める必要があります。
事前に準備をしておくと、スムーズに退職できます。
以下の書類は忘れずに確認しましょう。
- 退職願・退職届 – 所属機関のルールに従い、正式な手続きを取る
- 健康保険の切り替え – 退職後は国民健康保険に加入するか、新しい職場の保険に入る
- 年金の手続き – 公務員共済から厚生年金や国民年金へ移行
- 失業保険の確認 – 雇用保険に加入していた場合は、受給資格を確認する
- 退職金の申請 – 受け取れる金額や支給時期を事前に確認
必要な手続きを事前に把握しておくことで、退職後の生活もスムーズに進められます。
退職後の生活設計と資金準備
退職後の生活を安定させるためには、資金計画をしっかり立てることが大切です。
新しい仕事がすぐに決まるとは限らないため、以下の点を意識して準備を進めましょう。
- 生活費を見直す – 収入が一時的に減るため、無駄な支出を減らす
- 貯金を確保する – 少なくとも3~6ヶ月分の生活費を準備する
- 退職金の使い方を考える – すぐに使い切らず、計画的に活用する
- 転職活動のスケジュールを決める – 退職後すぐに次の仕事を探し始める
- 家族と相談する – 生活設計について周囲と話し合っておく
退職後の生活を見据えて準備することで、安心して次のキャリアに進むことができます。
転職後のキャリア成功のポイント
新しい仕事を成功させるためには、転職後の行動が重要です。
環境が変わることで戸惑うこともありますが、以下のポイントを意識するとスムーズに適応できます。
- 新しい環境に柔軟に対応する – 前職との違いを受け入れ、前向きに取り組む
- スキルアップを意識する – 研修や勉強会に積極的に参加する
- 職場のルールを把握する – 早めに職場の文化や方針を理解する
- 積極的にコミュニケーションを取る – 同僚や上司との関係を良好に保つ
- 仕事の成果を意識する – できるだけ早く成果を出し、信頼を得る
転職後にスムーズに馴染むことで、新しい環境でも成功を収めることができるでしょう。
まとめ

公務員保健師を辞める理由と転職のポイントについて解説しました。
退職を考える際に、以下の点を押さえておくことが重要です。
- 公務員保健師を辞める理由 – 仕事内容のギャップ、人間関係の悩み、給与・待遇の不満、ワークライフバランスの問題
- 退職前に考えるべきこと – 転職の目的を明確にする、退職後のリスクを理解する、転職市場の情報を集める
- 転職先の選び方 – 産業保健師、病院・クリニック、民間企業、フリーランスなど幅広い選択肢がある
- 円満に退職する方法 – 上司への伝え方、引継ぎの進め方、退職手続き、資金準備が重要
- 転職後の成功ポイント – 新しい環境に適応し、スキルアップを意識しながら働く
退職は大きな決断ですが、しっかりと準備をすれば、新しい道を前向きに進むことができます。
後悔のない選択をするために、今できる準備を始めましょう。







